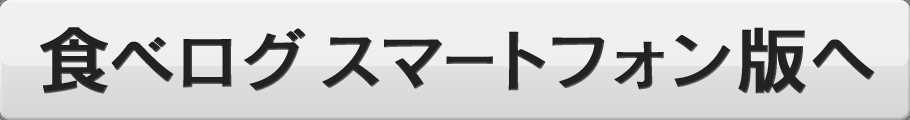門司だ。
関門海峡を隔て本州と対峙する交通上の要地。大化元年に文字の関が置かれ古代より発展したものの、明治迄の間、注目されることは殆ど見られなかった。
明治22年、築港会社が設立され、門司港は特別輸出港(米・麦・麦粉・石炭・硫黄に限定した輸出港)の指定を受けたことが契機となり、大きく発展を始める。
明治20年に創立された九州鉄道は明治22年に九州初の鉄道として博多-千歳川仮停車場間開業、明治24年に門司駅(現門司港駅)迄東進、海の玄関口と陸路が結び付くことになる。
地域的に筑豊炭田を控え、其の石炭の積出し港として、大陸貿易の基地として、貿易港の地位を築き、第二次世界大戦前は神戸、横浜、大阪に次ぐ全国第4位の貿易港となる。
貿易港、九州の玄関口として興隆を極めた門司だが、昭和17年に悲願でもあった関門鉄道トンネルが開通したため、門司港駅を経由せずに本州との行き来が可能になったこと、戦後中国との貿易衰退により、急速に其の地位を失うことになる。
昭和63年、門司港駅舎が国の重要文化財に指定されたことを契機に地区内に残る歴史的建造物を生かした観光地としての整備を行い、平成7年に門司港レトロとしてグランドオープンする。
旧大阪商船門司支店(国の登録有形文化財、現在、門司港ブランド雑貨店、わたせせいぞうと海のギャラリー等が入る)、北九州市旧門司三井倶楽部(国の重要文化財・門司区谷町より駅前へ移築、アインシュタインメモリアルルーム・林芙美子資料室等が入る)、北九州市旧門司税関、旧三井物産門司支店、門司郵船ビル(旧日本郵船門司支店)等、大正時代を中心とした建造物が多く残っている。なお、北九州市大連友好記念館は北九州市により整備された歴史的建造物の複製建築物である。
門司港レトロ地区には日本唯一の歩行者専用のはね橋がある。全長108㍍で、船が通る時は約24㍍の親橋と、約14㍍の子橋が水面と60度の角度に跳ね上がる。平成5年10月に開通したが、周辺の景観にも融け合っており、単純に見ていて飽きない場所である。
前回訪問は平成25年10月。
門司港駅がリニューアルしたことの他、門司港駅付近にあった旅館群芳閣の入り口横に建てられていたバナナの叩き売り発祥地の碑は平成26年2月に旅館が解体されたことを受け門司港駅前広場に移転、昨年60周年を迎えた関門トンネルの人道県境表示が変更等、時間の経過と共に変化が見られた。
今回はスケジュールの都合上、訪問が出来なかったが、前回訪問時に九州鉄道記念館はみっちりと見学した(笑)
*
《北九州市旧門司三井倶楽部》
https://tabelog.com/rvwr/pii/diarydtl/158465/《平成25年10月》
https://tabelog.com/rvwr/pii/diarydtl/158464/《和布刈神社》
https://tabelog.com/rvwr/pii/diarydtl/158463/《関門トンネル(国道2号) 人道》
https://tabelog.com/rvwr/pii/diarydtl/158462/《下関》
https://tabelog.com/rvwr/pii/diarydtl/158461/