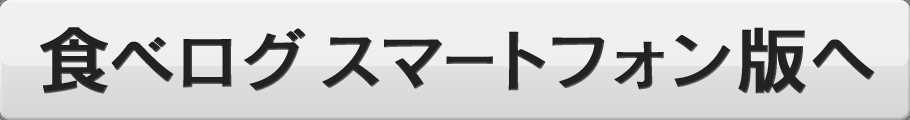3月3日日曜日
◎今日は何の日?◎
●ひな祭り
ひな祭りとは、平安時代の京都の風習だった子供の無病息災を願う上巳の節句(じょうみのせっく)と、ままごとの遊びが江戸時代初期に融合し、女の子のお祭りになったといわれています。
ひな祭りという呼び名は、小さな人形で「ままごと遊び」することを「ひいな遊び」と呼んでいたのが語源です。
はじめは京都の上流階級の家だけの行事でしたが、しだいに民間の行事となり、やがては地方へとひろまっていきます。
ひな祭りは江戸時代中期にかけて年々盛んになり、人形やひな壇もどんどん派手になっていきました。
当時は等身大の人形をかざったひな壇もあったといいます。
ですが、1721年(享保6)に、ぜいたくな生活を規制する当時の江戸幕府によって、ひな人形の大きさは24cm以下とさだめられました。
ひな祭りのことを別名で「モモの節句」といいますが、それは当時の旧暦の3月3日は、現在の4月上旬にあたり、ちょうどモモの花も開くころだったからです。
また江戸時代、ひな祭りの日には、銭湯でモモの葉をお風呂に入れた「桃の湯」に入るのが流行していました。
昔話の桃太郎が鬼を退治するように、植物のモモには災いをおいはらう効能があると信じられていたからです。
みなさんも、ひな祭りにはモモの入浴剤で「桃の湯」を楽しんではいかがでしょうか。
●耳の日
日本耳鼻咽喉科学会が1956(昭和31)年に制定。
「み(3)み(3)」の語呂合せ。また、三重苦のヘレン・ケラーにサリバン女史が指導を始めた日であり、電話の発明者グラハム・ベルの誕生日でもあります。
耳や聴力への関心を高め、聴覚障害の予防・治療を徹底する為の記念日。
●平和の日
1984(昭和59)年の国際ペンクラブ東京大会で、日本ペンクラブの発案により制定され、翌1985(昭和60)年から世界中で実施されました。
「女の子の健やかな成長を祝う雛祭りは平和の象徴である」との考えから。
●女のゼネストの日
1997(平成9)年から全国各地の実行委員会が実施。
男女共同参画社会を目指し、「男女平等基本法」制定を求めて女性が立ち上がる日。この日が女の子の節句であることから、この日に実施することになりました。
1996(平成8)年に来日したアイスランドのフィンボガドチル大統領の演説がきっかけになり制定されました。アイスランドでは1975(昭和50)年と1985(昭和60)年に「女のゼネスト」を行い、何万人もの女性が仕事を放棄して首都レイキャビクに終結し、これを契機に初の女性大統領が誕生しました。
●三の日
日本三大協会が1993(平成5)年に制定。
日本三大協会は、「三種の神器」「日本三景」等、日本で古来より三つで括ると安定すると考えられたのはなぜか、等を研究している団体です。
●桃の日
1999(平成11)年に日本たばこ産業(JT)が、同社の製品「桃の天然水」のPRの為に制定。
●金魚の日
日本鑑賞魚振興会が制定。
江戸時代、雛祭りの時に金魚を一緒に飾ったことから。
●結納の日
全国結納品組合連合会が制定。
結婚式の「三三九度」から。
●ジグソーパズルの日
「3」という数字は、表と裏とを組み合わせるとピタリと嵌るジグソー風な形をしていることから、3月3日となったもの。
ジグソーパズルは手と頭とを使い、楽しく遊びながら脳の健康を保ち、集中力を向上させるものとして、子どもからお年寄りまで幅広い人気があります。
これをさらに多くの人に親しんでもらおうと、ジグソーパズルを扱う各社で構成される「ジグソーパズルメーカー会」が制定しました。
●1603年
日本橋が開通。主要街道の起点となり、以来日本の道路交通の中心に。
●1860年
桜田門外の変。江戸城桜田門外で大老・井伊直弼が水戸浪士らに襲われ死亡。
●1923年
アメリカでニュース週刊誌『タイム』が創刊。
●1999年
『だんご3兄弟』のCDが発売。爆発的なヒットに。
●2001年
スポーツ振興くじ(サッカーくじ)「toto」が全国発売開始
●2005年
西武鉄道の証券取引法違反で前会長の堤義明が逮捕。
●2006年
第1回ワールド・ベースボール・クラシックが開幕。
◯今日の誕生日◯
村山富市(第81代内閣総理大臣・1924)
ジーコ(元プロサッカー選手・日本代表監督・1953)
栗田貫一 (ものまねタレント・1958)
宮台真司(社会学者・1959)
マッハ文朱 (タレント・女子プロレスラー・1959)
こんにちは☆
ひな祭りですね。
そういや、昔小学校の給食に菱餅(ひしもち)が出てきたような。
ひな祭りに食べるものって?
あと食べたのがひなあられ。
白酒は飲んだことないし。
こんな情報が、
『縁起の良い意味が込められたひな祭りの食べ物』
ひな祭りには古くから伝わる伝統的なお祝い料理があり、春の訪れを伝える旬の食材が使われています。
代表的なものとして、はまぐりの吸い物や菱餅(ひしもち)、ひなあられや白酒(しろざけ)、ちらし寿司などがあげられますが、それぞれの料理や色にも縁起の良い意味が込められています。
昔の人ならではの風情ある由来を知ると、よりいっそう意味をもってひな祭りが楽しめそうです。
●はまぐりの吸い物
はまぐりは、平安時代には「貝合わせ」遊びなどで知られ、ひな祭りの代表的な食べ物です。
はまぐりの貝殻は、対になっている貝殻でなければぴったりと合いません。
このことから、仲の良い夫婦を表し、一生一人の人と添い遂げるようにという願いが込められた縁起物です。
●菱餅(ひしもち)
緑、白、ピンク(紅)の3色の餅を菱形に切って重ねたものを飾ります。
色の意味にはいくつかの説があり、
緑は「健康や長寿」、
白は「清浄」、
ピンクは「魔除け」を意味する説と、
緑は「大地」、
白は「雪」、
ピンクは「桃」で「雪がとけて大地に草が芽生え、桃の花が咲く」という意味が込められているという説があります。
緑餅は増血効果があると言われるよもぎを混ぜ、白餅には血圧を下げると言われるひしの実が入り、ピンク餅は解毒作用があると言われるクチナシで色をつけています。
また、菱形は「心臓」を表していると言われ、災厄を除こうという気持ちや、親が娘の健康を願う気持ちが込められています。
ひなあられ
餅に砂糖を絡めて炒った、ひな祭りの節句の代表的な和菓子のひとつです。
ピンク、緑、黄、白の4色でそれぞれ四季を表していると言われています。
でんぷんが多く健康に良いことから「1年中娘が幸せに過ごせるように」という願いが込められています。
白酒
もともとは桃の花びらを漬けた「桃花酒」というものが飲まれていたと言われています。
桃は邪気を祓い、気力や体力の充実をもたらすということで、薬酒のひとつとして中国から伝えられました。
江戸時代からは、みりんに蒸した米や麹を混ぜて1カ月ほど熟成させた「白酒」の方が親しまれるようになりました。
「白酒」はアルコール度数10%前後のお酒で大人しか飲めないので、子どもにはノンアルコールの「甘酒」がおすすめです。
●ちらし寿司
ちらし寿司そのものにいわれはありませんが、えび(長生き)、れんこん(見通しがきく)、豆(健康でまめに働ける)など縁起のいい具が祝いの席にふさわしく、三つ葉、卵、人参などの華やかな彩りが食卓に春を呼んでくれるため、ひな祭りの定番メニューとなったようです。
その他にも、願いごとが叶うと言われるさざえや、はまぐりの代用品としてあさりなどの貝類もよく登場します。
野菜では、芽を出すものが喜ばれ、わらびやよもぎ、木の芽などをおひたしや浅漬けにしたり、白酒に浮かしたりして楽しみます。また、子どもたちにはよもぎ餅や桜餅などが、春の香りがいっぱいで喜ばれそうです。
今年のひな祭りも、女の赤ちゃんが初めて3月3日を迎える初節句のお祝いや、子どもたちを囲んで家族や友人とパーティーを催される方も多いのではないでしょうか。
ぜひ、ひな祭りならではの縁起のいいメニューを取り入れて、子どもたちの末永い健康と幸せを願ってみませんか。
食卓の会話も弾んで、おなかだけでなく、心まで満たされそうです。