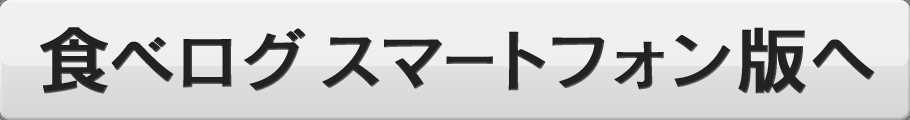
レビュアーの皆様一人ひとりが対象期間に訪れ心に残ったレストランを、
1位から10位までランキング付けした「マイ★ベストレストラン」を公開中!
2位
3回
2021/02訪問 2021/03/09
すしログ:遠方からでも何度も足を運びたくなる名店!京都府京丹後の縄屋
京都市内から120km離れている京丹後にあって、全国から食通を集める名店、縄屋さん。
僕は2015年4月に初めて伺った時に魅了され、5回ほど足を運んでいます。
縄屋さんはコロナ下の2020年7月にリニューアルを行われ、「薪料理の日本料理店」に生まれ変わりました。
訪問した結論としては、内容が以前からガラリと変わっていて、意表を突かれました。
魚菜料理縄屋とは?吉岡幸宣さんの魅力
縄屋さんのある京丹後は上述の通り京都市内から120km離れていて、車で2時間、電車で3時間半の場所です。
ご主人の吉岡幸宣さんは仕出し業を営むご家庭に生まれ、大阪と京都で修業されました。
名店「和久傳(わくでん)」で6年間腕を磨かれた後、地元の京丹後に「魚菜(さかな)料理縄屋」を2006年にオープン。
つまり、僕が初めてお伺いした時で既に9年が経過していたわけですが、足を運ぶ度に良い意味で期待を裏切られるので、毎回惚れ直します。
ただ、今回は仕事の精度だけでなくスタイルも変えられていたので、好きになる前にちょっとした戸惑いを感じました。
しかし、帰りの車中で反芻する内に矢張り好きになっている自分を見つけました。
吉岡さんの御料理は、もともと派手でも豪華でもありません。
しかし、美しく、どんな派手な料理よりも印象深い。
食材の持ち味を引き出しながら、他の料理人が出せない風味の組み合わせや食感を生み出す御料理です。
主な調理の特徴としては、極めて独自性の高い火入れや野菜出汁の使用、食材の食感の工夫など。
そして、自家製の調味料を組み合わせることで、唯一無二の御料理とコースが編み出されます。
縄屋さんの御料理は、東京で主流の日本料理とは真逆であり、高級食材を多用しなくても成立しています。
むしろ、それ以上の魅力を与えてくれる御料理で、心と胃袋に染み渡るとともに、土地の魅力を伝えてくれます。
東京で主流の日本料理のような、牛肉に海胆、卵料理や椀ものにトリュフ、蟹や帆立にキャヴィアと言った組み合わせは、分かりやすい足し算でしかありません。
甘みや脂分の掛け算や、香りのドーピングを使えば、誰しもが「旨い」と錯覚する「濃厚な味・香り」になります。
しかし、料理としての奥行きは浅い。
結果的に、そのような料理は料理人の調理哲学が浅薄である事を露呈します。
反対に、吉岡さんの御料理は、使用する食材の一番の美点に着目し、その美点を引き立てるために味、食感、香りを組み立てられています。
創作性が高いのに抑制されていて、抜群のバランス感覚です。
個人的に、このような引き算の美学を敷衍した御料理こそが、最先端の日本料理なのではないか?と感じます。
西洋料理は足し算を行う料理なので、西洋的なモダンガストロノミーを採り入れる日本料理だけを「最先端」と礼賛する行為は、日本料理の本質を見逃す浅い分析なのではないでしょうか。
縄屋さんのスペシャリテと薪火日本料理店としての今後
初めてお伺いした時から今までスペシャリテであり続ける御料理は【こなれ鮓(ずし)】です。
これは発酵させていない酢飯をお粥状にしたもの。
魚に添えられるソース的な存在で、穏やかな酸味、お米の甘みと香りが魚を引き立ててくれます。
鮨職人でない人間が鮨を握るのは、はばかられる…と言うお気持ちから生まれたそうです。
以前「試行錯誤して生み出した」と仰っておりましたが、その甲斐あって、一見すると素朴ながら一口で記憶に残る味わいの新たなスシに昇華されています。
【こなれ鮓(ずし)】の発想自体がユニークであるだけでなく、魚の魅力も巧みであるからこそ美味しいスペシャリテ。
見た目は握り鮨ではありませんが、握り鮨も酢飯と魚の仕事が調和して完成形となるので、料理の設計自体は握り鮨と同様です。
そして、もう一つ着目すべきは、魚の火入れです。
吉岡さんのそれは「火入れが巧み」と言うレヴェルではなく、もはや「独自の火入れ」です。
日本料理の若狭焼、中国料理の脆皮のような「皮のパリパリ食感としっとりした身のコントラスト」に留まらず、身にも食感のグラデーションがあります。
その結果、一皿で食感の多様性と火入れの違いによる味の変化を度々楽しませてくれます。
中心部はレアに仕上げられ、食感は艶かしくも旨味が活性化されていて、調理技術で新しい料理を生み出されている事に驚嘆します。
新たに薪料理のお店に改装すると伺った時は、真っ先にこの魚の火入れが浮かびました。
以前はスチームコンベクションオーブン(ラショナル製)と炭火による火入れでしたが、薪火でどう変わるのか?
大変興味深く訪問したところ、更に堂に入っていました。
スチコンを使用されているかは伺いませんでしたが、かつての火入れと酷似しているので、恐らく使用されているのだと思います。
さて、改装後のお店はオープンキッチンのカウンター中心で、奥に薪が燃えています。
以前の奥まった個室風のカウンター席とは趣が異なり、開放感がアップしました。
「薪料理」と聞くと、スペインのアサドール・エチェバリ、日本だと神戸のbb9(ベベック)が頭に浮かびます。
しかし、日本料理で薪火とは、非常に珍しい。
その理由は、伝統的な炭火の方が火力が高いところで安定するためでしょう。
吉岡さんが薪火を用いてどのような表現をされるのか…
今後も目が離せない京丹後の名店だと再認識しました。
縄屋さんのコースの詳細
コース価格については現在、6,000円と12,000円の2本になっています(+税サ)。
野菜は自家菜園と地元の有機農家のものを使用し、魚は京丹後の地魚と全国の名生産者(逗子の長谷川大樹さんなど)から仕入れておられます。
調味料は京丹後のものを多用され、お酢については宮津の飯尾醸造さんのものです。
薪火日本料理店となって初めての訪問は、以下の内容でした。12,000円のコースです。
最初の火で炊いたご飯
海鼠の茶碗蒸し
お造り:ヒラメ、鯵、甘海老
椀:鮑、蕗の薹餅、菜の花、白味噌仕立て
九絵(クエ)の焼きもの
鰯のこなれ鮓
猪の背脂、自家菜園の野菜の薪火焼き
猪の赤身、きんぴらゴボウのソース
黒大豆と毛蟹のお粥
黒文字のアイス、焼き芋ソース
紅芋酢ソーダ250円
飯尾醸造さんの紅芋酢を用いたソーダ。
最初の火で炊いたご飯
お米と水の美味しさを伝えてくれる一品目でスタート。
海鼠の茶碗蒸し
京丹後で旬の海鼠(ナマコ)を用いた茶碗蒸し。これが感動的な味わい。
海鼠は非常に柔らかく、トゥルン!と舌の上で踊り、ぷちりと千切れる。
磯らしい海鼠の香りを楽しませながら。
卵の香りも強く、滑らかで一体感の高い茶碗蒸し。
お造り
ヒラメ、鯵、甘海老の3種類で、全て調理を施したもの(生のままでない)。
ヒラメには海鼠から出た海水を煮詰めた塩を振り、鯵は山桜の葉で和えて、甘海老は海老味噌で和えて丸大根で挟みスイバをあしらっている。
ヒラメは寝かせてむっちり、ねっちりした食感で、ヒラメの旨味から顔を覗かせる海鼠のかすかな香りが印象深い。
鯵には桜の香りが軽やかに移り、実に心地良い。
甘海老は甘みと食感を楽しませつつ、スイバの香りが味を引き締める。
全て仕事を施した刺身である点が、縄屋さんの魅力。
椀
鮑、蕗の薹餅、菜の花、白味噌仕立て。
鮑は薄い衣を付けて揚げて、提供前に薪火で炙る調理。
蕗の薹餅は香りと苦味が白味噌にピッタリ!
九絵(クエ)の焼きもの
クエ出汁のソースと黒大根、付け合せはほうれん草。
これは前述の通りの吉岡さん流の火入れだが、流石!
皮はバリバリで香ばしいが、身の中心をレアに仕上げて、クエらしいむっちりした食感も残す。
ソースはクエの旨味をストレートに味わえ、野菜の風味が穏やかにアクセントととなる。
鰯のこなれ鮓
付け合せはキャベツと実山椒の塩漬け。酸味と甘みが絶妙に合わさる一皿。
こなれ鮓のお陰で鰯の脂が上品にまとめられている。
猪の背脂、自家菜園の野菜の薪火焼き
地元醤油組合の醤油の絞りかすをまぶして提供。猪の脂の甘みと野菜の美味しさをストレートに楽しめる。
醤油の絞りかすは香ばしい。
猪の赤身、きんぴらゴボウのソース
猪は非常に味わい深くて旨い上に香りが良い。「きんぴらゴボウのソース」は香りが正にきんぴらゴボウで、猪との相性が抜群。
野菜は飯尾醸造さんのお酢で和えている模様。
黒大豆と毛蟹のお粥
〆がお粥と言うのも意表を突かれた。
黒文字のアイス、焼き芋ソース
黒文字は和菓子を頂く際の楊枝に加工される木だが、香りが非常に良い。
爽快感のある香りはアイスにぴったりだ。
前回の2016年10月以来、1年ぶりの訪問となりました。
こちらは訪問する度に好きになるので、毎回記事を書いてしまいます(笑)
近場にあれば、もっと訪問したいお店…
今や東京の日本料理店の多くは価格が高騰し、
高級食材、果てはキャヴィアやトリュフを用いるまでになっておりますが、
こちらは日本料理の本質と日本料理のこれからの可能性を感じさせてくれます。
また、地方で日本料理を頂く喜び、
即ち、土地の風土を愛で、新たな食材と出会う喜びがあります。
本質的には、僕は高級食材でなくても独自の目利きを用いて食材を仕入れ、
「そこに行かねば頂けない料理」に仕上げる料理人が好きです。
「そこ」と言うのは必ずしも地方に限った話ではなく、首都圏であっても同様。
似通った食材でピンのもの(一級品)を貴ぶ食べ手も増えていますが、
それは偏に大海に漂う泡沫に等しい行為だと思います。
流行り廃りに右往左往するのは食べ手も料理人も愚の骨頂。
東京の日本料理バブルについては、食べ手が冷静になる必要があると、
敢えてキツく警鐘を鳴らしたいと考えます。
この度頂いた料理たち。
金目鯛
旨味が強く、たっぷりの胡麻の風味が盛り上げる。
金目鯛は塩で軽く〆ている模様。
金目鯛の下には錦糸瓜が敷かれており、
赤酢を用いてサッパリと金目鯛を抑制する。
酢の香りも料理のアクセントとなっている。
ウスバハギの肝、芥子酢味噌
カワハギとウマヅラハギは有名だが、
ウスバハギは一番知名度が低いのでは??
体長1mほどにもなるそう。
頂いてみると、非常にクリーミーで濃厚な口当たり。
そして、酢味噌の合わせ方が抜群。
辛めの芥子が鼻に抜ける。
それでいて、カワハギ科特有の香りも楽しませてくれる。
旨味の余韻はありつつも、上品な食後感を与えるので、
2品目であっても重くなる事は無い。
甘海老の塩麹漬け、オクラ
甘海老は塩麹で旨味が凝縮されており、シンプルに旨い。
オクラの青く爽やかな香りが穏やかに寄り添う。
キノコの茶碗蒸し
アミタケを使用。
頂いてみるとキノコの風味が活きており、実に旨い。
秋を感じさせる。
あしらいの栗の渋皮煮が、茶碗蒸しには意外な甘みでサプライズ。
どことなく粘りある食感は、キノコの粘性が活きてるのかな?
鰤とこなれずし、水茄子
名物のこなれずし。更なる高みに!
こなれずしの酸味とコク、鰤の脂の甘み、醤油餡、
全てが調和し、料理としての一体感が素晴らしい。
こなれずしが鰤の力強い旨味と香りを包み込み渾然一体。
醤油餡は良い醤油を使用しているのが明白。
調味料の凄さを調理技術で活かしている。
鰤の部位は腹と血合い寄りの数種類か?
白カジキの山椒焼き、天然舞茸
食欲をそそる香り!
そして、相変わらず素晴らしい火入れ!
カジキの脂は活性化し、身はレアに…
それでいて中心まで火(熱)が通っており、歯切れが良い。
味付けも秀逸で、優しい甘み(味醂)のある醤油味。
脂の旨味を炭の香ばしさが加速させつつ、山椒がピリリと引き締める。
和食のステーキですわ、こら。
とても、炭火だけで構築したとは思えない、神業。
ボリュームも多く、大満足です(笑)
イチジクの胡麻酢和え
あしらいはザクロ。
濃密な胡麻に熟成期間の長い酢を調合しているのか?
イチジクの甘みを爽やかに感じさせるセンス溢れる口直し。
ガザエビと人参の天麩羅
レアな火入れで、甘くぷりぷりに仕上げている。
人参は香り高く甘みあり、余韻に野趣。
とろみを付けたツユを少量振っている。
ツユはエビ出汁に軽く塩味を付けたものか?
お食事:栗おこわ
うーん、香り良い!栗の甘みもたっぷり!
お米(餅米)の炊き加減もバッチリ。
そして、香の物も留め椀も共に秀逸(本当に!)。
味噌は熟成されており味わい深く、椀種はもっちりした生麩。
ちょっとだけ菜っぱが入ってるところに心意気を感じさせる。
心意気と言うか、素朴な優しさと言うか。
水菓子
こちらの水菓子での強めの抹茶使いが大好きです。
餡も美味しいし。
この度も更に好きになりました(笑)
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:http://edomae-sushi.hatenablog.com/
行く度に好きになる、こちら縄屋さん。
毎回仕入れや細かな仕事、料理の構成などに変化が見られるため、
定期的に伺う喜びがあります。
この度は秋にお伺いしました。
金目鯛のこなれずし
定番の料理であり、安定感抜群。
金糸瓜は酢で合えているのか。
お米の旨味と金目鯛の甘み、金糸瓜の酸味が一体的になり美味。
揚げもの
むかごと銀杏、人参葉を用いたかき揚げ、人参の天麩羅に唐墨。
衣はサクッと軽やかで、銀杏の苦味やむかごの甘みと風味が堪らない。
唐墨は塩気が利いている。
全体的に「土の力強さ」を感じさせるかき揚げだと実感。
ノドグロ(赤ムツ)の焼き霜造り
かなり香ばしく皮を炙っており、甘みが引き出されている。
降り塩の塩梅も良い。
ヒゲソリダイのお造り
初めて頂く魚。
旨味が強く、香りは真鯛とはかなり異なる。
余韻があり、繊維質はシャクシャクと軽快。
九絵と鰆の焼きもの
こちらのスペシャリテとも言うべき、レアに仕上げた魚。
炭火を用いて旨味を存分に引き出したレアな火入れは絶妙の一言。
皮はパリパリ、さっくりとした食感。
クエは鰆よりも生に近い火入れで、魚ごとの味わいの引き出し方に妙がある。
そして、オリジナル調味料の野酵酢(やこうず)が旨い。
野菜を発酵させた調味料だが、発酵感は優しく、味わいに奥行きがある
漬け物をペーストしたような風味で、旨味がしっかりしており、酸味も強い。
しかし嫌みは無い冒険的なソースである。
大皿が提供前にしっかりと温められている点も好印象。
〆鯖と鯖の燻製
〆鯖は穏やかな〆加減で、酢の浸透も浅い。
焼きものとの類似性を感じさせるフレッシュ感、魚の提示の仕方。
鯖の燻製は香りの付け方が巧く、ふつふつと湧き上がる感じ。
実に上品。
蕎麦
なめこをあしらった蕎麦。
もっちりした食感の蕎麦で、ツユが良い。
鰹出汁に柚子と葱で爽やか。
キジハタと松茸の炊合せ
出汁、塩気共に強めだが、松茸の風味が強く、キジハタの甘みを引き出しているため、
バランスが取れている。
キジハタの香りも力強い。
栗ご飯
もち米を用いており、栗はふっくらで芳醇な甘み。
牛と舞茸のすき焼き風
牛はドライエイジングを掛けているそう。
比較的強い味付けだが、淡い味わいのご飯と同じタイミングである為、
嫌味にならない(すき焼きとしてはさっぱり目の味わい)。
日本料理で牛を出す際は、味付けの前に牛の脂の入り方が重要だと感じる。
水もの
いちじく、干しぶどう、ほうじ茶アイス。
いちじくの自然な甘みが活かされており、そこに干しぶどうの酸味が加わり、味を引き締める。
ほうじ茶アイスも過度に香りが強すぎず、全体的なバランスに優れている。
味、器、盛り付けの三拍子が揃った料理は、配膳される度に嬉しくなります。
またお伺いする日を楽しみにしつつ…
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
http://edomae-sushi.hatenablog.com/
【2016年1月】
こちらは昨年4月にお伺いしましたが、今回季節を変えて再訪しました(1月)。
結論から述べると、前回よりも満足度がググッと上がりました。
個々の料理の個性が強く出ており、個性が有機的に合致。
使用されている素材の幅も広がった印象です。
再訪して分かる部分(自分の問題)もあるかとは思いますが、
全体的なストーリー性と言うか、お店の輪郭がよりハッキリ分かる内容でした。
素材については従来は京丹後のものにこだわっておられたようですが、
現在は良い仕入れルートを見つけられたようで、他県のものも使われております。
ご自身の料理観に変化があったのかな?と感じました。
ご自身のイメージを具現化するために食材の幅を広げた。そのようなイメージです。
繊細さと華美を併せ持った個性的な日本料理で、
「やりすぎていない創作性」がやはり魅力的だと感じました。
盛り付けや器のセンスも非凡かと思います。
一つだけ特にオススメを述べるならば、魚の火入れ。
「魚はあまり食べない」、「焼魚なんて渋い」と思っている人ですら
確実に魅了されるであろう、繊細で柔らかな火入れです。
この度のコース内容。
【胡麻鯖の燻製と金目鯛のこなれ鮓】
【鮑と甘草の天麩羅】
【お造り(鯛、鰤)】
【北寄貝の椀】
【黒ムツの焼物】
【蛸のお造り】
【海老芋の煮物】
【冬鰻の椀】
【豆ご飯】
【水菓子】
【胡麻鯖の燻製と金目鯛のこなれ鮓】
一品目から変化球を繰り出してこられ、笑顔に。
胡麻鯖の燻製には柑橘類を混ぜた出汁が塗られているようで、
燻蒸香と酸味が程よく馴染む。
金目鯛のこなれ鮓は前回も頂いたが、やはり魅力的。
米の香りと甘みが金目鯛の脂の旨味を引き立てる。
【鮑と甘草の天麩羅】
鮑はきっちり香りがあり、柔らかく、噛みしめるとゼラチン質が舌に絡みつく。
良い火入れです。
甘草の若々しい青い香りも心地良い。
【お造り(鯛、鰤)】
これは共に素晴らしかった。
鯛は濃厚な香りを宿しており、噛み締めた時の鮮烈な風味が印象的。
やはり、西で頂く真鯛は扱い方が巧い。
そして、「味の勢い」で言うと鰤が上を行き、
感情に直接的に訴えかけてくる、荒々しい旨味。
濃厚な味わいながらに、脂はスッキリしており、頂いた後も清々しい。
包丁の入れ方が良い。
また、辛味控えめな辛味大根を添えているところにも、センスを感じる。
【北寄貝の椀】
超肉厚な北寄貝で暫し言葉を失う。
噛みしめると、ボディに反比例し決して大味ではなく、
北寄貝固有の甘みが滲み出てくる。
芳醇でふくよかな甘み。
北寄貝を活かすべく計算されて円味のある出汁も良い。
【黒ムツの焼物】
前回訪問した際に鰆で感じたが、今回の黒ムツも溜息がこぼれる程の火入れ。
超柔らか、ふわっふわに焼き上げており、魚の香りと甘みを満喫出来る。
炭火を使用しているようだが、ここまでコントロールされているのは見事。
粗く切ったクレソンには赤酢を使用。
【蛸のお造り】
武骨な盛り付けだが、歯切れが良く穏やかな甘みのある蛸。
付け合せは赤かぶ、津田かぶ。
【海老芋の煮物】
絶品。素朴な食材を合わせつつ、極めて強い印象を残す。
出汁は強めで、だからこそ海老芋の輪郭を強く浮き彫りにする。
素材そのものに近い形での提供だが、箸を入れると柔らかく、甘みが春を予感させる。
白魚、蕗の薹との相性は言わずもがな。
【冬鰻の椀】
鰻は肉厚で、穏やかな脂。
強すぎず、それでいて終盤の食欲を収めてくれる。
一品一品の流れに妙があり、これぞストーリー性だと感じる。
【豆ご飯】
豆の香りが芳醇で、贅沢な気持ちになる。
硬さも良く、炊き上げられた米の硬さとピッタリ合っているのが印象的。
一度炒っているのが香りの秘訣。
【水菓子】
豆、安納芋、金柑、蘇。
まさか蘇をデザートのソースにするとは。
マニアック過ぎです(笑)
お茶はクロモジ茶。
総じて、次回訪問するのが楽しみになる内容でした。
立地が立地とは言え、1万円ちょいのコースとは思えないクオリティです。
まだまだお若いご主人、将来的な進化を見届けたいと思わされました。
なお、器で印象深かったものがあり、作家を聞いたところ、
伊賀の岸野寛氏との事でした。
帰宅後早々に調べると、庶民には手が出しづらい価格(笑)
僕は器も好きで集めておりますが、
良いものはお店で堪能するようにしたいと思います…
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
http://edomae-sushi.hatenablog.com/
【2015年4月】
京都市内から考えると、非常に離れた場所にある日本料理のお店。
京都から車だと2時間半、電車だと4時間程度かかります。
離れた場所にありながら、わざわざ訪問すべき価値があると聞き、
機会を設けて伺いました。
お昼のコースは3,000円、6,000円、11,000円とあります。
折角なので一番上の11,000円を予約しておきました。
お店は、外観は民家的でありながら、内装はシックに纏められており落ち着きます。
テーブル席は大きな窓のそばで開放的で、
カウンター席は奥まった場所にありお昼でも隔離感があって対照的です。
カウンター席で一人頂きました。
頂いたコースは
【葉山葵と鱒の燻製】、【穴子とうるいの椀】、
【お造り(平目、鬼海老、あまどころ)】、【鰆の塩焼き】、
【赤目河豚とコゴミの揚げ物、ゴマ酢】、【金目鯛のこなれ鮓】、
【筍、アスパラ、蛤の炊きあわせ】、【叩きわらびご飯】、
【蓬のソルベ】
料理を頂いての感想は、
1. 創作性が高いが、適度なところで抑制されており、嫌みが無い
2. 素材のクオリティは非常に高く、同時にこちらならではな調理も楽しめる
といったところ。
やりすぎず、「抑制」する感覚こそ日本料理人のセンスかと思いますので、
ご主人の「ギリギリの冒険」とも言える料理は頂いていて気持ちが良いです。
奇抜な事をやっていないのに、明確なオリジナリティを構築しております。
頂いた料理の詳細は下記の通りです。
【葉山葵と鱒の燻製】
強い酸味の葉山葵と、しっとりな鱒の燻製が非常に合う。
【穴子とうるい】
穴子は地物。塩の利かせ方に妙があり、芳醇なゼラチン質を満喫。
【お造り(平目、鬼海老、あまどころ)】
山菜・あまどころは茎に甘みがあり、葉先には爽やかな苦味。風味に豆っぽさがあり面白い。
鬼エビは秀逸。快感とも言えるシャキシャキした身から迸る甘み、香り。
付け合わせのワカメのソースも美味。
【鰆の塩焼き】
付け合わせはクレソンに赤酢。
火入れが絶妙で、脂が豊かに滲む。
炭の香りも食欲をそそる。
【赤目河豚とコゴミの胡麻酢】
虎河豚よりも旨いとも言われる赤目河豚。
その判定はさて置き、何より、こちらも秀逸な火入れ。
シャクシャク、ぷりぷりした身からじわーっと旨味が滲む。
胡麻酢も抜群に合う。白眉。
【金目鯛のこなれ鮓】
米の香りと甘みが心地良い。
塩気もベストと言える。
【筍、アスパラ、蛤の炊きあわせ】
筍は甘み、香り、食感が巧く引き出されている。
【叩きわらびご飯】
醤油ベースの餡。
【蓬のソルベ】
爽やかな蓬の香りで、非常に印象的。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
http://edomae-sushi.hatenablog.com/
3位
2回
2017/10訪問 2021/05/03
約2年ぶりの訪問となった和喜智さん。
入り口を入ると、バカラの水晶招き猫が!
銀座の鈴木さんにも鎮座する招き猫ですね。
相変わらず、店内には良い香りと穏やかな空気が流れております。
再訪して感じた点は、
より攻めたタネの構成になっている事と、
やっぱりシャリが美味しいという事。
2年前も一品一品が強い存在感を示していましたが、
構成的には旨味をふつふつと高め満足感に繋げているように感じました。
しかし、今回は初手から力強いタネを連発され、キレッキレ。
とは言え、味覚のバランスが取れており、
抑制(引くところで引く)も施しているため、決して食べ疲れません。
シャリは前よりも酢を穏やかにしていますが、
北海道の鮨店のシャリとしては赤酢強めでインパクトがあります。
硬さや温度は完璧に近い。
握りも流麗なモーションで、速く、手数が少ない。
前回、「将来的に進化するシャリかも」と記しましたが、
2年ほどでここまで飛躍されているとは、正直なところ驚きました。
東京を除く東日本ではトップクラスの鮨であり、
個人的に福岡のさかいさんと双璧をなすと感じた次第です。
おまかせは2016年9月から税込21,470円となったそうですが、
頂いた後の満足感は高く、
下手なお店でそこそこの金額を支払うよりも
圧倒的に賢いお金の使い方だと思います。
この度頂いた日本酒。
まる田・特別純米、二世古・特別純米。
まる田は初めて呑んだが、端正なキレの中にまろみがあり、
米の旨味もある、良きスターターであった。
牡蠣と湯葉の茶碗蒸し
卵の甘みにホッと寛ぎ、出汁の塩梅も良いなぁと思っていると、
牡蠣のフレイバーが追いかけてきて高まる。
牡蠣は割と大ぶりで、むっちりとろりとした食感。
酢橘の皮は極僅かに使用しており、抑制が利いており良い。
鰤
羅臼産、10kg。
脂がきめ細かく、旨味に加えて鰤らしい酸味も感じさせる。
ぷりぱつな食感。旨い。
蒸し鮑
鮑から出たエキスに葛を打ったソース。
鮑の香りと旨味が滲み出ており秀逸。
下に仕込まれたシャリの酸味と肝の上品な苦味がベストバランス。
また、シャリの「硬さ」が食感を増やしている。
海胆
釧路産。問答無用で美味い。
ボタン海老
超立派なサイズのボタン海老を塩辛のように漬けている。
熟成で甘みが強められており、それを発酵が感が包み込む。
凄い旨味!
かと言って口に残らず、媚びない。
九絵、舞茸、白菜
舞茸で秋の香りを感じせ、
九絵の力強い風味と脂ならびに食感が主役の座に付く。
白菜の食感と甘みがアシスト。
鮟肝と奈良漬
言わずもがなのベストマッチ(笑)
旨味、風味、食感において調和が取れている。
鮟肝は黒酒(鹿児島の特産)に漬け込んでいるそう。
この後、握りに移行します。
毛蟹
初手からパワフルな一貫を手渡しで!
毛蟹は風味豊かで繊維が存在感を示す。
実に良い余韻だ。
旨味にしても、香りにしても。
蟹味噌も混ぜているため、磯が口に満ち溢れる。
大葉に乗せて握っているが、香りの転移は無い。
縞鯵
熟成を掛けて旨味を強めつつ、シャリの酸味と完全一致!
素晴らしき熟成の仕事。
頂いた後に尋ねたところ、3kgのものを10日間との事であった。
ボタン海老
すんげえ甘み!
そして、食感はブチブチ、とろんとろん。
食感の二重奏で溶けてゆく。
寝かせているもののボタン海老らしい食感が活きているところがポイント。
産地は礼文島との事。
金目鯛
もの凄い脂の旨味!
熟成を掛けている事は明白だが、食感を残しバツバツ感が良い。
炙りも皮下の脂を活性化しつつ香りを付ける程度で、抑制を感じさせる。
鮪トロ
熟成による強い旨味があるが、酸味も生きており美味しい。
北寄貝
漬け込み。
超肉厚で甘い!そして、歯切れも良い。
いくらと海胆
海胆の甘みを、いくらに付けられた軽い醤油が引き締める。
この素材の組み合わせはいくらの漬け込み次第では、
旨味が過多にもなり、醤油が主張しすぎる事にもなる。
シンプルでありながら、高い計算を感じさせる。
ガリ
ここで登場!
ストレートな酸味、そして辛味が一度場をリセットする。
キンキ
標準和名キチジ。北海道を代表する高級魚。
炙って香りを付けているが、力強い脂の旨味が軽く凌いで来る。
勢いある旨味と香り。
なんと、一晩干して(脱水して)食感を強めているそう。
初音鮨の鮪大トロ炙りを超える、脂の多いタネを用いた個性派仕事。
白身魚なので脂の性質的に上品であり、同時にパンチ力もある点が凄い。
椀
ボタン海老の出汁で旨い。
穴子
超絶とろんとろん。
甘みが酢飯の酸味を包み込む。
産地は予想通り対馬。
シャリとのコントラスト的には江戸前や瀬戸内のものよりも良いかと思う。
魚体は130gほどで、骨が障らないサイズを求めておられるそう。
鉄火巻き
肉厚な切り付けの鮪を使用。
海苔の食感と香りが良く、そこに鮪の鉄分が来て、旨味が広がる。
上質な鉄火巻き。
玉子
しゅわふわな食感。
ボタン海老を使用し、余韻が長く、香りは上品。
前(甘海老を用いた伊達巻)よりもデザート感が強い。
再訪が楽しみな名店です。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
こちらはすし善にほど近い、円山公園にある鮨店です。
この瀟洒な一角は札幌の一大グルメエリアとなっております。
ご主人は東京の街場寿司の出身ですが、全国を熱心に食べ歩かれ、
個性あふれる鮨を作り出しておられます。
「自身の理想とする鮨まではまだまだ…」と謙遜されておりましたが、
既に唯一無二の仕事も幾つか生み出されております。
着目すべきは仕事のセンス。
過剰なことはやらず、ギリギリのところで抑制されている印象を受けます。
それが奏功し、かなり上質なタネを入れておられますが、
損なうことなくタネを活かし、個性を表現する事に成功しております。
40代半ばで名声を高めておられるご主人。
これからの進化が楽しみです。
札幌で伺うべき鮨店は、こちらかと思います。
シャリは赤酢を二種類使用され、酸味が強く、エッジの利いたシャリです。
酸味を利かせつつ、砂糖も使用している為、尖り過ぎずにまとめておられ、
ハラリとほどける硬さ、粘度は非常に優れております。
米の香りも結構強いですが、嫌味にならずに一体化しております。
個性を出しつつバランスに長けた美味しいシャリです。
とは言え、試行錯誤されているそうなので、将来進化しているかもしれません。
なお、使用されている山葵も質が高く、静岡産の極太サイズ。
ガリも辛味を出した鋭い味付けで、その味付け故に途中で出されます。
この度の訪問時には縞鯵と帆立の間に出てきました。
蒸し鮑
函館産。包丁を入れた時に立ち込める香りこそ、鮑の魅力。
まさしく馥郁たる香りが鼻孔をくすぐり、食感を官能的に高められる。
火入れは絶妙で柔らかく、一口かじれば濃厚なゼラチン質と旨味に舌が惑わされる。
身に秘めた微かな苦みが美味しく、逆に肝は爽やかな味わい。
蝦夷バフン雲丹
利尻産。一粒が巨大で、香り、食感ともに申し分ない。
粒がしっかりと存在を主張し、舌を愛撫するように旨味がとろける。
真子鰈
函館産。面白い事に、肝ポン酢で頂く。
身はプリプリで甘みが走り、ポン酢の程よい酸味も上品。
肝を爽やかに食わす仕事。
ゴマサバ
淡路産。藁で炙り焼き。
皮下脂肪がもの凄く、今の時期の「鯖」として非常に魅力的。
とろっと脂が滲み、浅葱と生姜の使い方も抑制されており爽やか。
ツブ貝
肝ソース。食感、香りが非常に強く、余韻が長い。
キンキ味噌
兜の肉や骨まで使用した味噌。
塩分が控えめなのにお酒を進ませる、上品な酒肴。
甘みと香りがたっぷりで、かすなか骨の食感が気持ち良い。
キンキ焼物
皮はパリパリで。身はジューシー。
申し分ない火入れ。
この後、握りに移行します。
烏賊
鹿の子切り。ねっとりとした食感、甘みが非常に深い。
甘鯛
旨味が極めて強く、酢橘の使い方も巧い。
鰺
比較的珍しい、酢〆(≠酢洗い)。
酸味が香りと甘みを強調する、良い仕事。
トキシラズ
頂いて、その脂の質に驚く。
聞くところによると、3kgほどの魚体で、ほぼ鮭児との事。
皮目を軽く炙っているところにセンスを感じ、昆布で軽く〆ているところも白眉。
香り、甘み、食感の全てが揃った仕事。
縞鰺
10日熟成。口当たりが良く、香りも十分。
帆立海苔挟み
稚内産、海苔は愛知の青飛。
鮪トロ
三厩産。まろやかなコクがあり、香りよりも旨味が鮮烈な印象。
丁寧にタネの温度を戻されており、旨味の伝達、口どけに奏功。
北寄貝
炙り加減が非常に良い。腹まで届くような香りで、甘みも深い。
ホッカイシマエビ
かなりの上モノが入ったので生で、との事。
ブドウエビ
白眉。氷温熟成3日を経て、海老味噌で漬け込んだ卵と食す。
深い緑色の卵は見た目にも美しく、味わい的にはほぼ完璧。
「海老の新たな仕事」とも言える鮮烈な一貫。
椀
じゅんさいを使用しており面白い。
出汁はやや強めの鰹で、積丹産の岩海苔が香しい。
穴子
神奈川産(小柴?)。煮ツメはさっぱり。
伊達巻き
甘エビを使用。
素材のクオリティのみならず感動的な仕事が多く、満足の一言です。
鮨店では珍しく日本酒が進んでしまい、計三合。
(二世古・純吟・彗星、大信州・純吟、山法師・純米大吟醸)
申し分ない食事となりましたが、お会計は22,150円。
お会計は22,150円となり、少々お値段が張る印象ですが、
北海道で頂いた鮨の中では一番美味しく、
他の料理店と比べても訪問する価値があると感じました。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
4位
1回
2017/06訪問 2021/05/05
兵庫県は三田にマニアック且つ本物の日本料理店があると聞き、
エス・コヤマさんと合わせて訪問しました(笑)
ご主人は雅号を持ち熹志 侑紀但(キシ ウキタダ)と名乗っておられ、
1946年生まれで、1973年に開店された料理一筋の方です。
お店は三田駅から少し歩いた場所にあり、
外観からするとプロの料理人も通うと言う通人向けのお店には見えません。
内装もカジュアルで、小料理店と言った風情。
しかしながら、料理を頂いてみると、
食が好きな人であれば「何だこれは!?」と驚きを覚えるに違いありません。
僕はこう言ったギャップが大好きです。
こちらで使用されている食材は一級品揃いで、調理は一見するとシンプル。
しかし、シンプルさの中に玄妙な手腕が発揮されており、
舌に乗せた瞬間に広がる味覚の構成は極めて多層的で、官能すら覚えます。
足し算によって味を多層化するのは少しセンスがある方であれば出来る事ですが、
ご主人の料理には攻めの姿勢の背後に引き算の調整が感じられ、
一級食材が活き活きと精彩を帯びております。
本当の「引き算の料理」とは、素材を熟知し、
幾重にも手を加えた料理である事を体感させてくれます。
まだ若輩の自分ですが、早くしてこちらの御料理に出会えて良かったと実感しました。
ワインに精通する若主人・小西智允(こにしさとちか)さんの今後のご活躍も楽しみです。
三田は大阪からならば比較的行きやすい場所なので、
今後もタイミングを見計らってお伺いしたいと思います。
御料理に関してお話を伺ったところ、ご主人の口から出た、
「(半世紀近くやって)やっとここまでですわ」と言う謙虚なお言葉の裏に、
並々ならぬ努力の足跡と強い自負心が窺い知れ、非凡なる才能を感じ得た次第です。
尚、こちらのお店で頂ける日本酒もまた非凡。
奥丹波・山名酒造のお酒はその年で一番良いものを毎年30本入れておられ、
一杯目に頂いた一年前の雄町はしっかりした苦味とキレの後に甘みが広がる佳き味わい。
貴の純米大吟醸ヴィンテージ2014と2015の飲み比べには痺れました。
2015年は決定的に奥行きが薄く、旨味、苦味、香りが2014に及ばない。
2014は凛とした気品があり、年ごとに圧倒的に違う事を体感させて頂きました。
ここまでの仕入れは、長年培われた信頼関係と、
お酒への深い造詣が無ければ、実現出来ないでしょう。
頂いた料理は下記の通りです。
海胆豆腐
ねっちりとした食感に、濃厚な海胆の風味と磯の香りが立つ。
昆布を利かせた出汁に山葵を溶かしている。
どっしりした存在感ながらに爽やかな印象も与える海胆豆腐。
尚、海胆の産地は淡路。
鯵の棒寿司
〆た身は旨味たっぷりで香りが芳醇。
酢飯は優しい甘みと酸味が加えられており、鯵の〆加減に合っている。
三度豆と人参の胡麻和え
胡麻の風味がとても強く、シャキシャキした食感も心地良い。
甘みは抑えられており、お酒に合う。
お造り
驚嘆を覚えるアブラメ(標準和名アイナメ)!
ぷりぷりぷりっと非常に心地良い反発の後に、パツッ!と弾け、
甘みがたっぷりと舌に広がる。
いやはや、圧倒的な旨味。
塩、ちり酢、醤油もあったが、何も付けずに立て続けに頂いてしまった、
思わず興奮してしまったが、和歌山のケンケン鰹、明石のアオリイカも美味。
特にケンケン鰹は雄々しい血の香りに妙があり、旨味も十分。
ちなみに、上記アブラメの産地は明石。
椀
更に嬉しい事に、アブラメの椀。しかも、大ぶり。
切り付けが独特で、皮に垂直に薄く包丁を入れており、繊維のほどけ加減が抜群。
じゅんさいも素晴らしいクオリティで、産地を伺ったところ東広島。
吸い地は出汁、塩気ともに控え目で双方を活かす。
特にじゅんさいの瑞々しさが際立っており、清廉な気持ちに導く椀。
鰻の焼きもの
地焼きでふんわりと仕上げ、身のぷりぷり感も楽しませる焼き加減。
香りとゼラチン質が素晴らしい。
「香り」と言っても決して「臭い」」ではなく、鰻の良い香りである。
炭も良い備長炭を使っていると思われ、燻蒸香も相まって香り高い。
聞けば、須磨海の海の鰻であった。
付け合せのゴボウも非常に甘く美味しい。
トマトの冷菜
炊いたトマトに豆腐とモッツァレラチーズのソースと変化球。
濃厚だけどバランスが良い。
それは出汁と少々の酢橘が引き締めてくれているからだろう。
鮟肝
トロトロととろける食感の鮟肝!
ごく僅かに蒸して炊いてるのかな?
鮑と小芋の炊き合わせ
鮑は柔らかくも旨味しっかりで、軽い苦味と余韻がある。
しかし、スッキリとした食後感。
小芋はとても甘い。
昆布を強めて素材の旨味と甘みとを活かしている。
鮑の蒸し時間は5時間との事。
蛸の酢のもの
蛸は甘みが強く、包丁の入れ方が良い。
歯切れが良い上に、コリコリ感も楽しめる。
土佐酢も良い塩梅の出汁加減も酸味。
三田牛と破竹
初夏のタケノコの苦味と香りが牛の脂の甘みにとても合う。
嫌みの無い牛肉の使い方。
お食事
お米がとにかく美味しく、甘みしっかり。
水も良い事が分かる。
自家製のちりめんじゃこも風味豊か。
水菓子
マスクメロンと肥後グリーンとともに、
Royal Lochnagar(12 Year Old?)のオールドラベルを少量用いているそう。
メロンをそのまま頂くよりも嬉しい水菓子。
玉露
京都宇治。圧倒的な旨味を持つ玉露で、心地良い余韻に浸る事が出来る。
上記料理と、前述の日本酒以外に長珍・禄純米大吟醸、
白隠正宗・純米大吟醸斗瓶取りを頂き、お会計は2.1万円弱。
内容を考慮すると非常に優れたコストパフォーマンスです。
あまり良い言い方ではありませんが、
こちらが本当の「分かる人には分かるお店」だと体感しました。
日本料理が大好きな人、日本の食材が大好きな人、
日本酒が大好きな人はきっと感銘を覚えるお店だと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
5位
1回
2017/04訪問 2017/04/18
食通の方お二人から同じくらいのタイミングで強くオススメされての訪問。
3万円オーバーの高級中華は腰が重くなってしまいますが、
中国料理通の方曰く、損の無い内容だと。
よって、今回意を決して訪問しました。
結論から言うと、圧倒的な満足度。
質、量ともに高級中華としては極めてハイレヴェルで、
ノンストップの大興奮とともに感動を抱いた次第です。
特に魅力的だと感じた点は以下の3点。
1. 確かな中国料理の高い技術をベースに、新たな調理法を生み出している、
2. 日本の食材を用い、中国の調味料と合わせ、新たなる中国料理とする事に成功、
3. 強い味付けの料理を繰り出しても舌が疲れぬ味覚、塩分、油分のコントロール。
そして、ノンアルコールとアルコールを混ぜたペアリングも料理に精彩を与え、
満足度を上げる装置として効果的に機能しております。
なお、おまかせのコースは18,000円で、ペアリングは8,500円〜。
そこに税サが加わります。
頂いた料理。
竹蓀譲文蛤汤【はまぐりをキヌガサタケに詰めて】
艾茼鸡冠饺【蒸し餃子】
麻辣鸡【蒸し鶏の麻辣ソース】
海蜇皮【くらげ】
醉虾【酔っぱらいボタン海老】
雪菜百页【雪菜と布豆腐】
云白肉【豚薄切り香料ソース】
龙凤汤【雉と鰐の蒸しスープ】
四川排骨【梅香豚の四川の香り炒め】
葱烧甲鱼【すっぽん葱煮込み】
姜香炒青梗菜【青梗菜、新生姜の香り炒め】
脆皮鸽子【小鳩胸肉、腿肉】
乾烧鲜鱼【スジアラ唐辛子煮】
春天锅巴【春の香りのおこげ】
桂花柑橘【桂花と柑橘】
温冷杏仁豆富【杏仁豆富、二つの温度で】
樱花汤圆【桜の香りの茹で団子】
中国語を打つの疲れた〜(笑)
【はまぐりをキヌガサタケに詰めて】
桑名産の蛤を使用。
味わいの前に食感のギャップが魅力的。
キヌガサタケがしゃくりと弾けると、蛤の身と蒸した卵白が違う食感を与える。
そして、蛤のストレートな旨味が充満し、ゼラチン質のような密度の高い旨味が舌を甘やかせる。
生姜を利かせつつ嫌味になっておらず、蛤の香りや苦味は出ていない。
小体な料理ながら、厨师(シェフ)の技量を力強く体感させる逸品だった。
【蒸し餃子】
愛媛県産のよもぎ茶とよもぎを用いた蒸し餃子。
蓋を開けた時の香りが良い!
噛み締めると餡はジューシィで、鶏の酸味に鹹蛋の塩気と風味が合わさる。
過剰な味付けを行っていないが印象深く、中国料理で大切な「香」を、
日本の野草を以って楽しませてくれる。
【豚薄切り香料ソース】
【蒸し鶏の麻辣ソース】
【くらげ】
【酔っぱらいボタン海老】
【雪菜と布豆腐】
【豚薄切り香料ソース】は超薄切りで圧倒される。
聞けば、手切りとの事!
極薄であっても豚の香りが良く、しっかりと甘みもある。
梅香豚を使用する意味のある云白肉である。
通常の云白肉はどちらかと言うとタレの味付けで食わせる料理だが、
これはタレが素材と技術を活かしている。
タレは辛味と香りが良いバランス。
甘みも付加しているが嫌みが無く、軽い花椒と八角の香りが食欲をそそる。
そして、辣油の辛味が肉の脂の丸みを強調する。
尚、キュウリも極薄切りに切られ、瑞々しさと歯切れが素晴らしい。
百頁(布豆腐)は軽い爽やかな酸味があり、レモングラスかと思うも、馬告を用いているそう。
「馬告」は台湾名で、山胡椒として知られ、中国の南方でも使用される。
百頁に個性を与えるスパイスのチョイスと行き過ぎない使用量。
蒸し鶏はかなりしっとりした食感で、低温調理か?と感じさせる。
自身も家で口水鸡を作る際に低温調理を試みるが、
やはり滑らかな繊維のほどけは麻辣のソースとの相性が良い。
辣は割と強め。
クラゲは生海苔の香りがアクセントとなり、シャキシャキ、コリコリした食感は快感の一言。
当日分だけ茹でているそう。
醉虾はボタン海老を用いているだけあり、濃密な旨味である。
【雉と鰐の蒸しスープ】
このスープには広島の日本酒・雨後の月を合わせてこられ、これが良い。
勿論、スープ自体も秀逸。
キジ出汁は珍しいが、澄んでおり上品ながらに強い旨味が舌に馴染む。
ワニのジャーキーを用いているところも面白く、野趣を与える。
雲呑もキジ肉を使用。
最後に紹興酒を少し振っているそうだが、言われなければ気付かなかった。
この上質なスープに雨後の月が甘みを添え、相乗効果を感じさせた。
【梅香豚の四川の香り炒め】
宮崎県・五ヶ瀬の釜炒り茶であるみねかおりを合わせる。
炒め物の味付けは酸麻辣。
よって、お茶の苦味がキレを与える。
豚肉はホロッとしつつ、みっちりした繊維質。
脂身はトロトロで衣サクサクと、実に良いコントラスト。
酸が豚の脂を強調し、中毒性の高い味わい。
かなり花椒を用いており、インパクトの有る炒め物。
【すっぽん葱煮込み】
岐阜の天然モノと沖縄の養殖モノの食べ比べ(写真奥の小さい方が沖縄)。
意外な事に沖縄の養殖モノは野趣溢れる香りを感じさせた。
岐阜の天然モノは繊維質の力強さが妙味。
何れにしても香りを残す調理であり、好印象を抱く。
味付けは甘みが控え目で、苦味が香ばしさを与え、醤油(老抽)も出過ぎていない。
この手の味付けは上海風にすると、こってりし過ぎてしまい、
得てして素材を味付けが超える事が多い由。
強い旨味とゼラチン質を含有するスッポンを活かす秀逸な味付け。
【青梗菜、新生姜の香り炒め】
野菜をコースに交えて頂くと、嬉しい。
良い箸休めとなり、新生姜も奏功。
東方美人のスパークリング茶を合わせ、香りと苦味で更に爽やかに。
【小鳩胸肉、腿肉】
白眉!中国料理の焼き物を知る人間にとっては、感激ものの火入れである。
バリッと気持ち良く弾けた皮から瞬時にジューシィな肉汁が溢れ、繊維は流体のようにほどける。
とにかく皮と身の食感のギャップが桁外れ。
スモークしているそうで、途中から燻蒸香が引き締め食の持続性を高め、最後にふわっと残る。
とにかく美味しくて感動した(笑)
鳩が苦手な人を一瞬で虜にする鳩だろう。
【スジアラ唐辛子煮】
四川料理で豆瓣鱼と言う魚の豆瓣酱(豆板醤)煮込みがあるが、それを洗練させた秀逸な料理。
使用する豆板醤には軽い熟成感があり、味付けは麻辣だが、スジアラの旨味が力強く競る。
実にパンチある旨味で、五島産のスジアラを巧く使っている。
皮は油で揚げる事により香ばしさを与えている。
セロリが入っており、香りのみならず食感を付加し良きアクセントになっている。
【春の香りのおこげ】
ホタルイカ、クレソンを用い、酢胡椒で味付け。
生海苔や微塵切りの蕗の薹が面白い取り合わせである。
【桂花と柑橘】
サイフォンで淹れた金萱烏龍茶とともに。
金木犀にブラッドオレンジを合わせた爽快なソルベ。
【杏仁豆富、二つの温度で】
北杏と南杏のブレンド比を変え、2つの温度帯で供する変態杏仁豆富(笑)
デザートは中国料理の弱点と指摘したのは鉄鍋のジャン。
こちらは前のソルベと言い、実に楽しませてくれる。
【桜の香りの茹で団子】
団子の餡に黒胡麻を用いているのか中華的。
お腹一杯になりました!
6位
2回
2017/12訪問 2018/01/12
7月に訪問して感動したフランス料理店。
半年と経たない12月に友人と再訪しました。
今回も10,000円のコースを選び、福島フルペアリング6,500円を付けます。
メニューリストを眺めると、食材名に期待が高まります!
・青首鴨、福島牛、川俣シャモ、野菜のコンソメ
・会津産栗ぽろたん、フォアグラ、白トリュフ
・いわき大豆、せいこがに、雲丹、いわき人参、いわき白菜
・郡山産ひらたけ、常磐沖天然車えび
・相馬原釜鰆、伊達市ゼネラルレクラーク
・ゆきちからの自家製パン
・白子、いわきサツマイモ、いわきレモン、完熟みかん
・フォアグラ、奇跡のいちじく
・いわき赤むつ、北塩原じゅんさい、原木しいたけ、いわきいぶり大根
・鮫川村産羊、ジロール茸、いわき人参、いわき長兵衛
・日光天然かき氷、鮫川村産ジャージー牛練乳、福島苺
ペアリング
・ふくしま逢瀬ワイナリー、シードル2016
・会津中将、純米大吟醸特醸酒
・いわきワイナリー、シャルドネ2015
・豊国酒造、純米大吟醸「超」
・いわきワイナリー、デラウェア2016
・いわきワイナリー、マスカットベリーA & メルロー2015
・国権酒造、純米大吟醸
結論として、再訪しても感動は色褪せず。
新たな福島の食材との出会いに歓喜しました。
1万円のコースとしては極めて秀逸であり、
東京から車で行っても元を取れる内容です。
【青首鴨、福島牛、川俣シャモ、野菜のコンソメ】
先ず、香りが良い。
食欲を刺激するのは香りだけに非ず。
牛肉の力強い旨味に野菜の甘みが均一的に接続され、
強いゼラチン質が舌を撫でる。
これはシャモ由来だろうか。
雑味が無く胃袋をダイレクトに刺激するコンソメ。
【会津産栗「ぽろたん」、フォアグラ、白トリュフ】
これまた香りが良い!
栗は温度と湿度をコントロールした冷蔵庫で糖度26℃まで上げている。
「ぽろたん」とは品種名で、加熱により鬼皮と渋皮が一緒に剥ける栗。
濃厚なフォアグラムースの味わいもさる事ながら、
ホクホクで香り良く甘~い栗が印象深かった。
【いわき大豆、勢子蟹、雲丹、いわき人参、いわき白菜】
ワタリガニのジュと大豆の豆乳で。
人参と白菜は数時間前に収穫したとの事で、野菜の香り強い!
…と思いきや、濃厚な風味の大豆が追いかけてくる。
しかし、味わいは決して重くない。
勢子蟹はジュレで固めているよう。
正直なところ勢子蟹単体は弱いものの、ソースが抜群に纏め上げる。
大豆が活きており、ワタリガニの旨味も奏功。
【郡山産ひらたけ、常磐沖天然車えび】
使用されるひらたけはある程度菌床栽培した後に
畑で栽培すると言う、変わった方法を採っている。
これにより、放射性セシウムの問題をクリアしているそう。
ひらたけは旨味を補強するようにバターと塩が巧みに用いられたソテー。
そして、海老との味の繋ぎにフランス産モン・ドール。
ウォッシュタイプの香りと濃厚な味わいが精彩を加える。
海老は強めの火入れで、噛み締めると香りが高まる。
【相馬原釜鰆、伊達市ゼネラル・レクラーク】
相馬の鰆は今が旬。塩で脱水した後、桜チップで燻している。
それをゼネラル・レクラーク(西洋梨)と一体化。
この梨は粒子が非常に細かく、みっちりしつつ滑らかな口当たり。
そして、フィンガーライムをアクセントに。
燻蒸香強めの鰆に梨の甘みとライムの酸味が加わり、個性的な味わいに昇華。
「攻め」のバランスの料理ながら、一体感が高かった。
日本酒甘み強くにがみはしり酸味なので料理と合う
【ゆきちからの自家製パン】
サクサク、もっちり。
【白子、いわきサツマイモ、いわきレモン、完熟みかん】
いわきレモンは生産量が少なく、2個くらいしかもらえないそう。
それをソースに使用している。
そして、寝かせたサツマイモのピュレに、白トリュフ。
白子の旨味に濃厚な甘みのサツマイモピュレが相性抜群。
レモンのソースは軽やかな酸味が上品に活き、香りもまた爽快。
【フォアグラ、奇跡のいちじく】
「奇跡のいちじく」は本当に奇跡的な味わい!
とろんとろんで、甘みしっかり!
香りは独特で、酸味もあるため後味を引き締める。
フォアグラは雑味や臭みが皆無で、比較的サッパリながらに旨みある。
レアな火入れも秀逸。
フォアグラと合わせるいちじくにはバルサミコの酸味を付加している。
【いわき赤むつ、北塩原じゅんさい、原木しいたけ、いわきいぶり大根】
赤むつは備長炭でレア寄りに仕上げており、炭の香りも気持ち良い。
出汁を詰めた缶には意表を突かれる(魚に掛ける)。
椎茸は霧吹きを使用せず、夜露だけで育てた「ド根性椎茸」との事。
グアニル酸と風味が強く、この缶詰ソースは塩気が穏やか。
魚部分に塩を強めに当てている。
【鮫川村産羊、ジロール茸、いわき人参、いわき長兵衛】
羊は9ヶ月。歯切れは良く、旨みが強く、臭み皆無。
燻蒸香が上品で、良い塩梅。
里芋(長兵衛)は粒子が細かく、トロトロで甘みが重たくない。
人参はトロッと焼き上げ、甘みに野趣が程良く混ざる。
【日光天然かき氷、鮫川村産ジャージー牛練乳、福島苺】
相変わらず専門店を超えるかき氷!
ジャージー牛の練乳もクドくなく、氷を盛り上げてくれる。
【マイティリーフ】
また伺います。
以前、農林水産省料理マスターズの受賞料理店を調べた時に、
全国の名だたるお店の中でも特に気になったコチラ。
かつてはカジュアルな洋食寄りのお店だったようですが、
震災を機に業態ならびに方向性を一変。
萩春朋シェフは福島の生産者と繋がり、福島食材の魅力を発信し、
独自性の高いモダンな料理を構築しておられます。
こちらの魅力はコンパクトに集約すると2点。
即ち、知られざる美味しい福島食材に出会える点。
モダンガストロノミー的なエッセンスを加えつつ、
食材の魅力を最大化する事に成功している点。
食材の魅力、調理の魅力、プレゼンテーション、
全ての点において強い独自性を有しており、
あえて足を運ぶ価値のある地産地消レストランだと思います。
1日1組に限定されて提供されるスタイルも、
お客としては特別感並びにおもてなしの心意気を感じさせてくれます。
そして、非日常的な穏やかな空間に、癒やしを覚えます。
ところで、食材、調理の魅力は後ほど詳述するとして、
県外から訪問する方が否応無しに気になるのは、
福島食材の「安全性」でしょう。
結論から言うと、福島県で厳正に調査された食材は、
むしろ安全性が高いのは事実。
チェックが厳しいが故に安全性が保証されている状況です。
東電ならびに政府への不信感から福島食材を買い控えていた方は多いと思いますが、
真面目な生産者さんの手による福島食材は、まず安心出来る次第です。
未だに不安を覚えるのは消費者として自然な心理かと思いますが、
事実を知り、安心して頂く事が今後の福島への在るべき姿ではないでしょうか。
やや堅苦しくなってしまいましたが、福島食材の魅力を知ろうとするならば、
こちらのお店は最適だと思います!
お店には1万円、1.5万円、2万円のコースがあり、
この度は1万円のコースを頂きました。
下記の通り、圧倒的な満足感です(笑)
尚、料理名は素材から適当に付しました。
・生木葉ファームの空豆、車海老と赤海胆、福島牛コンソメ泡ホイップ
・会津産ホワイトアスパラガス、ふぁ〜むつばさのジャージー牛モッツァレラ、剣先イカ
・北塩原町佐藤さんのじゅんさい、鱧と黒トリュフのスープ
・ゆきちからの自家製パン
・甘鯛、白茄子、桑名産蛤と喜多方産サフランのソース
・フォアグラ、キヌア、樅山果樹園の佐藤錦ソース
・遠野鰻、いわきワインとスパイスの照り焼き
・草野純一和牛、花ニラ、アスパラガス
・有精卵液体窒素アイス、黒トリュフ
・四代目徳次郎の天然氷のかき氷、古山果樹園の桃
・ミニャルディーズ
・紅茶
そして、こちらにペアリング3種4,500円を。
【ふくしま逢瀬ワイナリー シードル2016】
林檎の香りがしっかりしており、味わいとしては媚びないキレがある。
甘くが非常に低くスッキリしているので、最初の一杯として実に良い。
【生木葉ファームの空豆、車海老と赤海胆、福島牛コンソメホイップ】
無農薬・有機農法で育てられた空豆。
旬以外のために畑1レーン分を購入し、瞬間冷凍しているそう。
そこに、千葉県産の天然車海老と赤海胆を合わせる。
初手から意表を突く味わいで、華やかな見た目以上に質実剛健な一品。
海胆の甘みにまろやかな牛のコクが寄り添い、
空豆の青々しい風味が引き締める。
車海老は風味が強く、香りがアクセントとなり、
やや強めに塩味を付けている点が全体のバランサーとなっている。
味覚の制御が取れたスターターである。
【会津産ホワイトアスパラガス、ふぁ〜むつばさのジャージー牛モッツァレラ、剣先イカ】
御料理が届いた瞬間に、アスパラガスの香りが立ち上がる…
頂いてみるとホワイトアスパラガスの甘みに烏賊の甘みが二重奏を奏で、
紫蘇やバジル麸、微塵切りの赤タマネギの風味、
ヴィネガーとグレープフルーツの液体窒素の酸味などが名脇役を演じる。
自家製モッツァレラは十分なコクがある。
【飛露喜・純米大吟醸】
次の御料理に合わせて日本酒と言う選択。
【北塩原町佐藤さんのじゅんさい、鱧と黒トリュフのスープ】
希少性の高いじゅんさいを用いた、日本料理の椀の様なスープ。
鱧の出汁がしっかり出ており、鱧の旨味に黒トリュフの香りが彩りを加える。
こちらのじゅんさいはヌル(周囲の寒天質の粘液)がタフ。
本体の食感は旬をやや過ぎているのでやや弱かったが、
スープとして使うと言う選択は最適だと感じた。
そして、日本料理の椀では攻めきれない領域の強めの塩が食欲をそそる。
とろとろなフランも椀の味覚構成と食感のバランス的に良好な存在。
そして、木製のカトラリーは口当たりが優しく、
スープの具材の食感に合った選択であると感じる。
【ゆきちからの自家製パン】
クラストはとことんカリカリで、クラムはふわんふわん軽くモチッ。
非常に香ばしく旨味も強いので美味しいパンだが、焼き上げから少しだけ置くと、
更に美味しくなるかもしれないなと感じた。
ただ、美味しいのでお替わりをたっぷり頂きましたが(笑)
【甘鯛、白茄子、桑名産蛤と喜多方産サフランのソース】
神経〆の甘鯛を松笠焼き(ポワレ)で。
ソースがチューブで供されるのは、モダンガストロノミー的面白さ。
ソースはサフランの香りが強く、蛤のコハク酸がグイグイと攻め込む。
鯛は皮下にねっちりした脂が潜み、美味。
白茄子は焼き茄子仕立てなので焦げの香りがアクセントとなっており、
タイムで洋風にアレンジされている。
ソースは温度帯的にチューブでなくても良いように感じたが、
ちょっとしたサプライズとしては奏功している。
【Bor Forrás Hajós Baja Blaufränkisch 2015】
マニアックなハンガリーワイン!
次の御料理の佐藤錦ソースとの相性は抜群であった。
【フォアグラ、キヌア、樅山果樹園の佐藤錦ソース】
佐藤錦のソースが秀逸。
レアでトロトロに仕上げたフォアグラにサクサクの香ばしいキヌア。
さくらんぼの良き酸味と穏やかな甘みが滲むソースが、
フォアグラをフォアグラ以上に飾り立ててくれる。
【遠野鰻、いわきワインとスパイスの照り焼き】
備長炭で焼き上げており、ふっくらトロトロな火入れ。
鰻は香りを楽しめる。
そして、ソースは鰻を活かすフレイバーで、
備長炭の香り付けの塩梅も良い。
【草野純一和牛、花ニラ、アスパラガス】
仔牛は1頭100万円超えで取引されていると言う、草野さんの和牛。
特別に飼育された処女牛を使用しており、格別なる贅沢。
強い旨味に加え、香りが極めて素晴らしく、酸味もあって実に美味しい牛肉。
オーヴンで火入れした後、炭火で炙っているようでカリカリした食感と香ばしさが付加されている。
レアに寄せず、赤身寄りの肉を活かす火入れで好印象。
タマネギの甘みを利かせ、旨味の強いソースは肉以上に付け合せの野菜に精彩を与えた。
【有精卵液体窒素アイス、黒トリュフ】
ふわっと溶ける中に濃厚な卵の甘み!
黒トリュフが差し障り無い。
【四代目徳次郎の天然氷のかき氷、古山果樹園の桃】
レストラン離れした完成度の高いかき氷!
デセールがかき氷とは、琴線に触れました。
しかも、フルポーション(笑)
古山果樹園の桃は格別であり、生産者さんは何と、
糖度32度の桃を作れる方だとか…。
驚嘆に値する。
この度頂いた桃も大変甘い上に香りも抜群で、
ソースも含めて印象深かった。
素晴らしい生産者と素晴らしい料理人の幸福な出会い。
またお伺いしたいと心から感じました。
7位
2回
2021/06訪問 2021/06/29
すしログ:全国屈指の鮎料理店!鮎で感動したい人は島根日原の美加登家へ!
島根県の内陸部である津和野町日原にあり、決してアクセスが良いとは言えないのに、全国から食通を惹きつける名店中の名店があります。
その名も貫禄十分、美加登家。
かつて島根県からご発注頂いた取材依頼でお伺いして、深い感動を覚えました。
▼取材記事
今が旬の鮎を味わう!島根の清流「高津川」を巡る食旅
そして、今回再訪して美加登家の素晴らしさを改めて実感しました。
日本人ならば死ぬまでに一回伺った方が良いのが、美加登家さんです!
全国で一つだけ!美加登家の鮎料理が凄い理由
美加登家が凄い理由は、使用する鮎のクオリティの高さもあり、それについては後ほど詳しくご紹介します。
美加登家の鮎料理が凄い理由それ以上に僕が凄いと感じているので、美加登家に伝わる鮎料理の仕事です。
鮎の魅力をあますところなく引き出す調理には目を瞠るものがあります。
特に、内臓の塩漬けである【うるか】を駆使する御料理は、初めて頂いた人のほぼ全てが驚くはず。
「苦くて、クセが強い」イメージの【うるか】を巧みに調味料のように使われるので。
そして、調理には奇抜なところや過剰な足し算が全くありません。
個性的な御料理を作るとしても奇抜な事を行わず、鮎の特性を熟知して料理されています。
研ぎ澄まされた感性に基づく調理。
その結果、美加登家の鮎料理は、鮎に苦手意識を持つ人すら魅了します。
鮎は古来より日本人に愛されてきた魚。
美加登家の鮎料理は古来の貴人ですら口にできなかった至高の鮎料理だと思いますので、我々現代人が頂けるのは本当に幸せなことです。
鮎は当て字を用いると「香魚」と書きます。
この理由は養殖モノの鮎では体感しづらく、天然モノを頂いて痛感します。
多くの「鮎嫌い」な方が挙げる苦手な理由は、大体下記のようなものでしょう。
生臭い
骨が当たる
海の魚の方が美味しい
これらは美加登家のような名店で天然モノの鮎を頂くと、全く別物であったのだと気づき、鮎の魅力に引き込まれるのは間違いありません。
結果的に以下のような印象になるでしょう。
香りが良い!
骨が気にならず、頭ごと食べられる!
海の魚とは異なる魅力がある!
美加登家の歴史さて、美加登家の創業は1934年(昭和9年)です。
島根県の山奥でのビジネスとして考えると、信じられない老舗だと言えるでしょう。
現在は先代2代目女将の山根紀江さんと、紀江さんの甥であり3代目板長の山根一朗さん、奥さんで若女将の由香さんが切り盛りされています。
女将さん、若女将の接客は非常に明るく、心が和みます。
その上、山根一朗さんも素敵な笑顔の方なので、ご家族全員が素敵だと感じています。
4代目板長となるご子息は京都の名店・緒方さんで修業中とのこと。
どうやら「美加登家の味」が継承されるようで、ファンとしては安心しています。
実は、美加登家は東京の新橋に支店を持っておられました。
屋号を「鮎正」と言い、1963年(昭和38年)に美加登家の創業者である山根正明さんが開きました。
日原は如何せん遠いので、「東京人にも高津川の天然鮎の美味しさを知って欲しい」と言う一心で開業されました。
当初は日原から鮎を移送するのに大変な苦労をされたそうですが、東京でも名店として認知され、息子の山根恒貴さんが2代目を継がれました。
以前、美加登家を訪問した際(2017年6月)に「鮎正にも是非訪問されてください」と聞き、訪問しようと考えていたところ、2018年12月に閉店されてしまったのです。
山根恒貴さんの体調不良が理由とのことで、残念です。
「鮎正」の閉店に伴い、東京には鮎の上質なコースを出すお店が無くなってしまったので。
しかし、美加登家は遠くとも東京からお伺いする価値のある名店だと、2度の訪問で確信しています。
未来永劫残り続けて欲しい、日本料理の至宝だと思います!
日本に残された清流、高津川の鮎の美味しさ
美加登家で使用する鮎は、そばを流れる高津川の鮎です。
高津川は日本で唯一ダムのない一級河川で、水質の高さで知られています。
樹齢1,000年を超す一本杉の根元に湧く泉「大蛇ケ池」が水源で、これはスサノオノミコトに討たれたヤマタノオロチの魂が宿っていると言う、神話の国・島根らしい伝承があります。
高津川は国土交通省が水質を調査する「清流日本一」に複数回選ばれていて、数年間王座を陥落したあとに返り咲き、地元の方の努力が偲ばれる河川です。
そのおかげで、間違い無くクオリティの高い鮎を頂けます。
雑味が全く無く、鮎らしい香りが上品も楽しめて、脂も程良く乗っている鮎を頂けます。
現地では一般的に、高津川本流の方は旨味に、支流の匹見川の方は香りに妙があるとの評価があります。
どちらが好みか食べ比べをすると面白いかもしれません。
美加登家では高津川本流の鮎に絞り、しかもエリアを限定して仕入れておられます。
さらには、数10匹の中から選りすぐってお客さんに提供されています。
結果として、「清流日本一」の高津川の中でもエリート中のエリートを頂けるのが、美加登家の鮎と言えます。
ちなみに、食好きな方でも鮎の生態を知らずに食べている方がいらっしゃるので、一応、記載しておきます。
鮎は秋に孵化した後、川の流れに乗って海に出て、プランクトンを食べて成長します。
そして、春に生まれた川へ戻ります。
川に戻った鮎の主食は、川の岩に生える苔。
苔を食べるため、「キュウリ香」とか「スイカ香」と呼ばれる鮎特有の爽やかな香りを纏うのです。
苔は川の水質や水流の状態の影響を大きく受けるので、鮎の味わいは川によって大きく異なるわけですね。
高津川はサステイナビリティが徹底されていて、漁期と子持ち鮎の漁獲が制限されています。
しかし、過去に比べて漁獲量が下がっています。
15年前は年間150トンほどあったものの、現在は47トンほどになり毎年増減を繰り返しています。
原因は乱獲ではなく、台風や大雨、気候の変化が主な理由のようです。
自然はどうしようもありませんが、消費者としては頂く時に感謝の念を忘れないでいたいものですね。
特に都会に住んでいると食材への感謝の念が薄れ、単なる「料理」として考えがちですが、食材と自然あっての食事ですから…
僕もこのように書く事で、自分を戒めたいと思うばかりです。
美加登家の立地と雰囲気
美加登家の立地はたびたび出てきている通り島根県の日原という場所にあります。
数々の食通をして「行きづらい場所」と言われますが、皆足を運ぶところが美加登家の凄さです。
御料理が美味しいことがもちろん主要因ですが、雰囲気が良いところも、遠方から足を運ぶ理由の一つです。
創業時は料理旅館だったので、威風堂々、大変趣のある建物です。
到着した瞬間に期待が高まる風格ですね。
尚、建物は1953年(昭和28年)に建てられた旅館であり、奥には1932年(昭和7年)当時の「旧館」も残っています。
現在は料理のみ提供されておりますが、往時を偲ばせる雰囲気もまた、唯一無二の魅力かと思います。
旧館は1932年(昭和7年)に建てられたそうなので、お店の創業よりも前。
本館も1953年(昭和28年)の建造と伺いました。
室内は使われている木材の質が高く、欄間も職人の腕を感じさせるものなので、優雅な時間を楽しめます。
こちらの空間に浸り、選び抜かれた鮎の御料理を頂いていると、遠方から伺って良かったと強く実感します。
美加登家が誇る、絶品!天然鮎コースの詳細
天然鮎のコースは6月から9月末までの期間限定です。
6月は香りが最も強く、7月以降は次第に脂が乗り、魚体も大きくなるところが特徴です。
コースは2つご用意されていて、11,000円、16,500円(税込、サービス料別途)となります。
ちなみに、他の時期も含めたコースの概要は以下の通りです。
島根和牛と花山椒鍋会席コース 時価(4月中旬~5月中旬)
高津川産天然すっぽんコース 18,150円(9月1日~9月30日)
子持ち鮎 生あぶりコース 16,500円~19,800円
松茸と子持ち鮎のコース 33,000円~(10月中旬より)
会席料理11,000円、16,500円(12月~5月)
ふぐコース養殖 16,500円~
ふぐコース天然 33,000円~
2021年6月の訪問記事:天然鮎コース(16,500円)の内容
天然鮎コース(16,500円)の内容はこちらです。
珍味:子うるか、苦うるか
御造り:鮎の背ごし
御椀:炭火焼き若鮎と冬瓜
焼きもの:鮎の塩焼き×3尾
煮もの:うるか茄子
強肴:うるか味噌揚げ、鮎の骨せんべい
酢のもの:鮎昆布〆、胡瓜、山芋、トマト
お食事:鮎めし、稚鮎の白味噌仕立て、香の物
水菓子:青梅の甘露煮のかき氷
この度頂いたお酒
古橋酒造、初陣純米吟醸
鮎酒
珍味:子うるか、苦うるか
鮎の器が可愛らしい。
…がサメに見えるのは気のせい??
子うるか(奥)は食感が良い。
オスの精巣とメスの卵巣を使用しているため、ぷるぷるな食感とプチプチする食感を楽しめる。
苦うるか(鮎の器)は秀逸の一言。
香りが抜群!
御造り:鮎の背ごし
初手から漂う香りが爽やか!!
お腹周りは脂があり、香りにも野趣が加わる。
旨みの強さに驚くせごしである。
水気を切って頂く。
薬味は茗荷、紫蘇の芽、高津川産の山葵。
椀:炭火焼き若鮎と冬瓜
洗練された吸い地に感動する。
利尻昆布と鮎の調和が素晴らしい。
鮎の旨味が強く、それを引き立てる出汁であり、塩気も完璧。
吸い口は酢橘で、洗練された椀。
焼きもの:鮎の塩焼き×3尾
肝の香りが強く、旨味もしっかりしている。
「まだ小ぶり」との事であったが、香りを楽しめるのは十分嬉しい。
また、特筆すべきは苦味が爽やかであるところ。
喉に残る苦味と旨味が印象的で、常に香りを楽しませてくれる。
ちなみに、こちらは蓼酢も美味しい。
鮎と上品に乳化するような妙味がある。
無思慮に作り蛇足となる蓼酢もある中、大変魅力的だ。
煮もの:うるか茄子
うるかのホロ苦さと香りを纏った茄子。
実山椒が利いていて、シンプルに旨く、香りも楽しませる。
ご飯に乗せて頂くと、なんとも郷愁を誘う喜びがある。
童心に帰ったかのような喜びだが、味わいはあくまでも大人の味だ。
強肴:うるか味噌揚げ、鮎の骨せんべい
白眉!
うるかをたっぷりと使用しつつ、香りと苦みが熱で穏やかになり、衣と一体化する。
ガリガリサクサクな衣の食感も良い。
これは本当に素晴らしい作品である。
酢のもの:鮎昆布〆、胡瓜、山芋、トマト
ここで登場する鮎の〆もの!
流れが嬉しいし、〆方が良い。
割としっかり目に昆布で〆ているのに、野暮ったさが皆無で、鮎の魅力を封じ込めている。
調味料は鮎出汁の土佐酢か?
お食事:鮎めし、稚鮎の白味噌仕立て、香の物
こちらの鮎めしは絶品。
鮎の香りが本当に良い。
白味噌仕立ての椀も素晴らしい味わいで、小鮎が入っているのが嬉しい。
もちろん香の物まで美味しい。
水菓子:青梅の甘露煮のかき氷
大変爽やかな水菓子。
鮎の後に嬉しい味わい。
日本でも有数の清流として知られる高津川。
一級河川では数少ない「ダムの無い川」となり、
国土交通省調べの「清流日本一」に過去に数年間連続で輝いております。
現地に行くと、成程、確かに澄んでおり、のどかな風景と共に印象に残ります。
その中でも、美加登家さんの鮎は高津川本流のものに絞られているのが特徴。
そして、エリア的にも日原から横田あたりまでに限定されているそうです。
高津川の支流である匹見川を好む方もおられますが、
本流と支流で味わいを変える点は鮎の面白さですね。
本流の方は旨味に、匹見川の方は香りに妙があるとの評価もありますので、
どちらが好みか食べ比べをすると面白いかもしれません。
鮎の好みは十人十色であるように感じますが、
鮎料理としての美味しさについては、こちらの美加登家さんは突出しております。
個人的に、鮎の魅力は塩焼きに収斂され、塩焼きこそが最高の調理法だと考えます。
最近は西洋料理、中華料理でも若手シェフが工夫を重ねて鮎の新たな魅力を引き出しておられ、
それはそれで大変美味しく、方々で楽しませて頂いておりますが、
塩焼きは鮎の妙味である香りをダイレクトに感じさせてくれる調理法であり、
純粋に肝と身の旨味に向き合う事が出来ます。
塩焼きが巧いかどうか、それこそが鮎を供する料理店の評価基準だと考えます。
そう言った意味で、こちらの焼きの技は全国でも上位に入るため、
河川ベースでの鮎を体感するならばわざわざ伺う価値のあるお店だと感じます。
ちなみに、虎屋 壺中庵さん、召膳 無苦庵さんの焼きも個人的に感銘を覚えるレヴェルでした。
とは言いつつも、こちらは塩焼き以外の料理も秀逸であり、
鮎を愛する方にとっては、終始笑顔が絶えない内容だと思います。
オーソドックスな背ごしに始まり、最後の鮎めしまで、
確かな日本料理の技術をもって鮎を余すところなく楽しませてくれます。
季節を愛でる喜びがあるお店です。
尚、建物は1953年(昭和28年)に建てられた旅館であり、
奥には1932年(昭和7年)当時の「旧館」も残っております。
現在は料理のみ提供されておりますが、
往時を偲ばせる雰囲気もまた、唯一無二の魅力かと思います。
頂いた日本酒
下森酒造・平家の里・純米吟醸、
古橋酒造・初陣・純米(塩焼きに合わせて)、初陣・純米吟醸。
鮎酒(古橋酒造&美加登家)
お酒に鮎の旨味と風味がじわじわと滲む。
頂いた料理は下記の通りです。
尚、鮎は6月~8月で月ごとに味わいと香りを変えます。
下記の記事は6月中旬となる事を特記致します。
更に厳密に言うと、川の水量や天候でも食味が変わるため、
本質的な鮎の比較を行う場合、
同じ川を「毎年」「6月~8月に毎月」訪問しなければ感じ取れないのではないか?と思います。
「○○川の鮎が素晴らしい」と言うのは、
鮎の一側面である事を念頭に置く必要があると感じる次第です。
うるか、子うるか
子うるかは、特有のぷにゅぷにゅな食感を噛み締めれば、香りと旨味が高まる。
こちらは発酵させていないので、さっぱりした味わい。
反面、肝を発酵させたうるかはパンチのある味わい。
ストレートな苦味が走り、鋭さがあるものの、旨味はしっかり。
鮎の香りも楽しめる。
一般的なうるかよりも塩分濃度が低いところが魅力。
鮎の背ごし
旨味に加えて香りが強い!
香りの源泉たる肝が付いていないのに、香りを十分楽しめる。
強い甘みが舌に広がった後、苔の壮快な香りが鼻に抜け、
軽い苦味が味を引き締め、柔らかな甘みが余韻として残る。
甘みの伝達が波状的で、非常に感銘を覚える味わいの背ごし。
繊維質のほどけも良い。
尚、使用する山葵は安蔵寺山(あぞうじさん)の麓のもの。
鋭い辛みの底に柔らかな甘みがある。
島根県と言えば「匹見山葵」も有名だが、こちらも美味。
鮎の清汁仕立て
吸い地は鰹、昆布、酢橘を軽く絞り、塩気は控え目。
椀種は冬瓜。
鮎は小さいが甘みがあり、冬瓜が腕に野趣を添えている。
小体な鮎の柔らかな旨味が次の焼きものへの期待を否応無しに高めてくれる。
鮎の塩焼き
前述の通り、こちらは高津川の鮎の中でも上モノを入れている次第だが、
焼きものに使う鮎は更に厳選しているとの事。
4名で伺ったところ、20尾から8尾を選び抜いているそう。
頂いてみると、圧倒的な旨味、甘みで、香りも強く残る。
身はホロホロ、皮はパリパリ、振り塩はベストとも言える塩梅。
高津川の鮎の美味しさと共に、卓越した焼きの技術を体感させられ、鮮烈な印象を覚えた。
うるか茄子
うるかの魅力がギュッと詰まった茄子の煮もの。
酒と味醂の甘みにうるかの苦味が滲んだ味の強い一品だが、
茄子の瑞々しい風味がクッションになる。
甘みと苦味のバランスが堪らない。
残った煮汁はご飯に掛けて頂く。
ある時に常連さんが所望されて編み出された提供方法だ。
鮎の揚げもの
こちらもうるかを用いた揚げもので、強めに利かせたうるかが油に合う。
衣はひたすらサクサクで、身はホロホロ。
鮎の酢のもの
〆に用いる昆布の使い方が巧く、鮎の旨味が凝縮されている。
土佐酢は甘みが控えめで上品な味わいで、酸味と鮎の旨味が綺麗に馴染む。
結構強めに〆ているが、しっとりな食感を残している点も良い。
鮎めし
鮎の香りと旨味に満ち溢れたごはん。
一粒一粒に鮎の存在感が染みわたり、お米の甘みと鮎の風味が一体化。
たっぷり用いられた鮎は全ての骨が取り除かれている。
卓越した味わいの鮎ご飯である。
留め椀の白味噌の塩梅も上品で、香の物も美味い。
水菓子
青梅と氷。実に爽やかな〆となる。
鮎のシーズン以外は天然モノのスッポン料理や
ツガニ(=モクズガニ、上海蟹の同族異種)料理を頂けるそう。
スッポンも産地の特質を反映する素材であり、
高級店でも養殖モノが主体となっているので、
いつか頂いてみたいと感じました。
敢えて訪問する価値のある名店だと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
8位
4回
2021/10訪問 2021/11/06
直近の訪問で頂いたもの(秋)
2021年10月に頂いたものです。
先付
天麩羅なかがわ三ツ葉と菊の花のおひたし
三ツ葉と菊の花のおひたし。
車海老×2
2尾連続で出てきて、異なる火入れなのがこちらのスタイル。
1尾目で、前よりも更にレア感がアップ!中心は透明なのに甘みが強い!!と思ったところ、2尾目で驚かされた。
よりレア感が強く、甘い。
前よりもコントラストが明白になっていて、親方の修練の証を見る!
車海老頭
安定感抜群。
これでお酒を飲むのが旨いんだよな〜と緊急事態宣言解除後の喜びを実感した。
鱚
巨大でホロホロな鱚は天麩羅で鱚を頂く喜びを心から感じさせてくれる。
鱚の旨味は本来淡いものであるが、十分に旨味を感じ、胡麻油(九鬼純正胡麻油)の香りが強烈にアシスト。
静と動を併せ持つ鱚の天麩羅である。
鱧
江戸前天麩羅では勿論のこと珍しいタネ!
キスの後だと鱧の少し野趣がある香りが活きる。
身質も異なり、ホロホロかつゼラチン質がねっちりととろけ絡まる。
旨味も活きている。
鮑
白眉!
衣はガリッガリ、そしてしゅわっと溶けるので、鮑を盛り上げ完全に寄り添う。
鮑の身はむっちり、ぷりぷり、そしてジューシィなエキスがじゅわっと溢れる。
その後、旨味と香りが力強く広がる。
中川親方の鮑は変化し続け、他にない魅力を高め続けている。
鮑の肝
鮨でも天麩羅でも鮑に肝がついてくると笑顔になるもの。
天麩羅の場合、ホロ苦さが落とされ肝の甘みを強く感じる。
モロッコインゲン
衣の香ばしさが広がった後に、凝縮されたインゲンの甘みと香りが炸裂する。
松茸
長野県諏訪、湖南後山のもの。
親方が切りつける時から香りが広がり、素晴らしい!
感動モノの香りだ。
頂いた後にも残るほど。
個体によって味が異なり、長い方は旨味が強い。
アオリイカ
アオリイカについては鮨よりも旨い食べ方だと感じる。
むっちり食感が加えられ、甘みがふつふつとこみ上げる。
鮨でも軽い火入れを行ってみると面白い仕事になるのではないか?
万願寺唐辛子
とろっとろで、甘い。
既存のイメージの食感とのズレは中川親方の天麩羅における妙味だ。
海胆大葉巻き
海胆の甘みが強く、ミョウバン臭さは無く、大葉も香りと食感共に良好。
海胆大葉巻きは当たり外れが大きいが、中川親方のものは大当たりだ。
海胆は浜中町カネキ木村の特選。
カボチャ
ホクホクで甘く、香りも良い。
メゴチ
後半でも美味しい白身!
これは天麩羅ならではなストーリーテリングだ。
香りが良い。
しかも、食感がむっちりしていて、効果的に脱水して揚げている。
穴子
サクッ!!
巨大な穴子を脱水して揚げていて、安定感が抜群の美味しさ!!
小玉葱
甘くて香りが良い。
蓮根と茄子
茄子はとろっとろで甘みが強い。
蓮根も香りが良い。
サツマイモ
超上質な焼き芋のようなサツマイモ。
天丼
天茶とも選べるが、赤出汁を求めて天丼を頼む確率が高い。
香の物もバッチリ美味しい。
タレ味の天麩羅は胃袋にダイレクトに突き刺さる美味しさだ。
実直に腕を磨く職人の姿は凛々しい。
決して奇抜な事をせず、ただ自らの技と向き合う職人さんのもとには、繰り返し足を運びたいと思う。
職人とは料理人とは異なり、一芸で技を極め抜く料理人である。
僕のライフワークである鮨は勿論、天麩羅にも同じような職人の粋がある。
天麩羅なかがわさんは、天麩羅において自身が通い続けたい、職人の粋を感じるお店だ。
天麩羅なかがわの親方・中川崇さんについて
親方の中川崇さんは天麩羅の名店の一つである、「みかわ是山居」で修業されました。
「みかわ是山居」は鮨の名店である「すきやばし次郎」の小野二郎さんが通うお店で、親方の早乙女哲哉さんは当代一の天麩羅職人の一人とされます。
新たな技を幾つも編み出され、「天麩羅は脱水作業」と言う名言が有名です。
中川さんは18歳の頃に早乙女哲哉さんの元で修業に入り、技を磨く事なんと17年!
2004年7月に築地で独立されました。
僕が初めてお伺いしたのは10年ほど前になりますが、伺う度に技を向上させておられ、同じタネなのに印象が違う!と驚かされます。
そして、他の天麩羅店を巡ることで中川さんらしい魅力を再認識するので、足を運ぶ喜びがあります。
中川さんの天麩羅の技で、個人的に特に凄いと思う事は主に3点です。
・海老における「みかわ流」の火入れの精度の高さ=高温の油でレアを保ちつつ水分を飛ばす脱水
・穴子における「みかわ流」の火入れの精度の高さ=「蒸す」と「焼く」を同時に行い過脱水を行う揚げの技
・鮑や虎河豚の白子などの食材を、天麩羅だけでなく他の調理法にも無い仕上げにする技
中川さんの天麩羅は、早乙女親方の昔の仕事を進化させている印象で、幾つかのタネについては既に御師匠を超えていると個人的に感じます。
或いは、早乙女親方は近年、火入れを変えた(ご自身の好みが変わった)とのお話もありますので、中川さんは原初の早乙女親方の仕事を色濃く伝えていると言えるかもしれません。
そして、中川さんの天麩羅は衣も強い印象を与えてくれます。
タネによって表情を大きく変える衣なのですが、押しなべて香ばしさが強く、高温の油を操る技が凄いと感じます。
タネをみっちりと包みこみ、隙間の無い衣は、タネと一体化し、香り、味覚、食感の全ての点で多層的なハーモニーを奏でます。
衣とタネの分断が無く、一体感があって、美味しさが波状的に広がる天麩羅です。
噛み締めていると、味わいが幾段階かに変化する魅力があります。
そして、全体を通してのタネと衣で織りなすストーリーテリングも絶妙。
ふんわりと軽やかにお仕上げる衣、香ばしくサクッと仕上げる衣など、衣で緩急に富んだストーリーを編まれています。
個人的に、天麩羅を愛する方ならば、全国でも訪問すべきお店の一つだと断言出来ます。
なかがわさんのコースの概要と予算
なかがわさんは凄腕なのにリーズナブルです。
メニューは昼の【梅】6,600円に始まり、【竹】9,900円、【梅】12,100円、【おまかせ】時価となります。
日本トップクラスの天麩羅店なのに、グルメな学生でも楽しめる価格帯なのは素晴らしい。
僕はいつも【おまかせ】を頂きます。
「時価」は怖いかもしれませんが、実際には他の有名店や東京の鮨店からすると大変リーズナブルです。
お酒を飲んで22,000円~23,000円くらいを見ると良いでしょう(冷酒は佐賀県・窓乃梅、常温は高知県・菊水)。
使用するタネのクオリティ、ボリュームともに充実しているので、価格に見合う満足感があるはずです!
直近の訪問で頂いたもの(冬)
2020年12月の訪問です。
今回頂いた天麩羅
サイマキ(2尾)
サイマキ頭(2尾)
鱚
ハゼ
銀杏
鮑
墨烏賊
虎河豚の白子
万願寺唐辛子
ハゼの卵巣(酒肴)
海胆の大葉挟み
カボチャ
穴子
アスパラガス
茄子
蓮根
サツマイモ
天茶、香の物
車海老(サイマキ)
「みかわ」流の火入れが更に堂に入っており、驚嘆する。
中心温度を人が甘みを感じやすい45℃から50℃の間に仕上げる技に加えて、余計な水分が飛び凝縮したような食感は絶妙の一言!
衣はしっとり、ふんわりかと思えば、さくりとほどける。
車海老の甘みと香りを強く感じさせ、衣の妙も味わわせる、中川さんならではな車海老だ。
車海老の頭
とにかく香ばしく、香りの凝縮感が素晴らしい。
鱚
みっしりした身はホロホロとほどけゆく。
淡白な鱚の味を活かしつつ、衣が美味しい事を実感させる。
初手からホロホロではない、しかし、鱚らしい繊細さを残す火入れ。
ハゼ
大型のハゼ!
野趣ある香りが心地良い。
身はホロッとほどける。
鱚よりも高温で脱水か?
それでいて鱚よりもホロホロ。
白身魚でコントラストを楽しませくれる天麩羅は意外に珍しいので、タネの構成が良いなと実感。
銀杏
一口目に広がるホロ苦さと香りが良い。
鮑
3年前に初めて頂いた鮑だが、これまた精度を上げられていてビックリ。
食感、香り、旨味の点において明らかに他の調理法では楽しめない表現に仕上げておられる。
鮑のむっちり感、火入れを行った事によるぷつりと切れてくにゅっと身をよじらせる食感、口に広がる鮑の旨味など、言葉を失う味わい。
これが、驚くきことに揚げ時間はわずか2分程度!
サイズによって時間を調整されているとは思うが、予想以上の短時間に意表を突かれた。
鮑をここまでの短時間で化けさせるとは。
墨烏賊
ぷるっとして、パツッと切れる墨烏賊らしい食感で、鮨と同じく江戸前らしい魅力を感じさせてくれる。
虎河豚の白子
親方は天然モノしか使わない。
大きく切りつけた肉厚な塊を、タンパク質が凝固するギリギリまで攻めて揚げる手法。
柔らかすきず決して硬くせず、中心まで火が「程良く」入ってクリーミー。
この程良さが絶妙。
写真は映えないが、味は格別!
真鱈の白子よりも上品な甘みで旨味は強い点が特徴であり、その特徴を魅力のレヴェルまで昇華させている。
万願寺唐辛子
香りと甘みが良い口直し。
ハゼの卵巣
柔らかいカラスミ状の塩辛で、酒を盗む盗む。
海胆の大葉挟み
前よりも味わいが洗練されていて、海胆の甘みも強く感じさせる揚げ加減に。
カボチャ
海胆の甘みからカボチャの甘みに自然に接続。
ホクホクで、香り高い。
穴子
超巨大な穴子を絶妙な脱水の技で仕上げる。
江戸前の穴子は状態が悪く、対馬産を使用されていた。
中川さんは対馬の脂が乗った柔らかい穴子にムチを打ち、決して甘やかさない。
その結果、引き締まった繊維質と気高い香りを楽しませる逸品に仕上がる。
アスパラガス
香りが良く、天麩羅との相性の良さを実感するタネ。
茄子
茄子も脱水され、初めてならば意外性を感じる味わいに。
蓮根
写真撮影を失念。茄子の後に食感が印象的で、香りも良い。
サツマイモ
天麩羅店におけるスイーツ的な役割のサツマイモ。
焼き芋のような妙がある。
天茶
いつもはかき揚げ丼を頼むことが多いが、天茶でスッキリと。
何回かお伺いしている、なかがわさん。
この度、松茸を求めて訪問しました。
2017年は松茸(キノコ全般)が全国的な不作で、
仕入れは運次第との事でしたが、無事に仕入れて頂けました。
しかも、岩手県・宮古産の上物。
穴子もそうですが、中川さんは天麩羅の技術のみならず、
仕入れの面でも楽しませてくれる職人さんです。
また、お目当ての松茸だけでなく、今回感銘を覚えたのが鮑。
鮨や日本料理で頂く「蒸し」とは異なる火入れを実現されており、
仕事の凄さに舌を巻いた次第です。
創作色の強い天麩羅屋さんも増えておりますが、
中川さんはあくまでも江戸前の枠組でオリジナリティを発揮されており、
実に硬派な天麩羅職人さんだと感じます。
いつ伺っても新しい発見が有るので、足を運ぶのが本当に楽しいです。
今回頂いた天麩羅。
・サイマキ(2尾)
・サイマキ頭(2尾)
・鱚
・鮑
・銀杏
・ハゼ
・墨烏賊
・松茸
・海胆の大葉挟み
・穴子
・アスパラガス
・茄子
・サツマイモ
・獅子唐(追加品)
・かき揚げ丼と赤出汁、香の物
サイマキ(2尾)
サイマキ頭(2尾)
相変わらず秀逸な仕事。
レアに仕上げつつ、甘みと香りを引き出す!
頭は香ばしく揚げ、コントラストを楽しませる。
鱚
カリ!と弾けた後、ふーんわり、きめ細かくほどけゆく。
鮑
非常に柔らかく、ぷりぷりしており、
甘みがジューシィに横溢する。
とにかく食感と旨味を最大限引き出す技術。
火を入れず生から揚げている(=天麩羅の仕事だけで勝負)のに、
上質な蒸し鮑に近い感動を与えてくれる、硬派且つ洗練された技。
銀杏
ねっちりと美味い。
苦味が酒に合う。
この食感は天麩羅ならでは。
ハゼ
野趣に満ちた香りを強い旨味が追い掛ける。
そして、軽い酸味がサラッと引き締める。
墨烏賊
これもまた絶妙な火入れ。
松茸
岩手県宮古産。
抜群!の香り!
松茸のクオリティは香りで明確に決まる。
香りのみならず、旨味の余韻も強い。
そして、歯切れの良さもまた特筆すべきもの。
縦に裂けるのはキノコなので言わずもがなだが、
横の歯切れの良さは天麩羅ならでは。
海胆の大葉挟み
揚げると磯の香りが引き立つ。
衣のサクサク感と大葉の香りの残し方が良い。
穴子
こちらの穴子の天麩羅は最高です!
野趣溢れる香りがあり、
まさか10月上旬にまだ羽田のこのサイズ!?と驚いて聞いたところ、
まさしく産地は江戸前羽田沖であった。
記憶に残り、また頂きたくなる穴子。
アスパラガス、茄子
アスパラガスは香り良く、ジューシィで甘みたっぷり。
天麩羅通の知人いわく、
野菜の中でも特にアスパラガスで天麩羅職人の腕が分かるとの事。
その意味では、中川さんは素晴らしい腕前。
根元の方はトロトロに仕上げ、意外性が有る食感。
茄子もトロトロで香り良く美味しい。
サツマイモ
カリィッ!衣が弾け、ホクホクしたサツマイモから、
甘みと香りがぶわっと広がる。
甘みを衣の香ばしさが制御する。
単に甘いだけで終わらないサツマイモの天麩羅である。
獅子唐
追加したところ、良い口直しになった。
かき揚げ丼と赤出汁、香の物
相変わらず美味しい。
その一言が全て(笑)
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:http://edomae-sushi.hatenablog.com/
数年前に訪問して以来、久々の訪問となりました。
師匠である早乙女親方のいらっしゃるみかわ是山居にお伺いした際、
なかがわさんの天麩羅を改めて頂きたいと強く感じた次第です。
なかがわさんは5,400円の梅(お昼のみ)に始まり、
夜でも7,560円のコースがあって一流の天麩羅店としては非常にリーズナブル。
ただ、この度は真骨頂を体感すべく、時価のおまかせを頂きました。
そして、頂いた感想としては、幾つかのタネは師匠を超えているのでは?と驚嘆を覚えた次第です。
或いは、早乙女親方は近年、火入れを変えた(ご自身の好みが変わった)との情報もありますので、
中川さんはより原初の早乙女親方の仕事を色濃く伝えていると言えるのかもしれません。
何れにせよ感動的な火入れのタネに出会え、心からの満足を抱きました。
衣のコントロールも巧みで、ふんわりに仕上げつつ軽やかなもの、
香ばしくサクッと仕上げているものなど、緩急に富んだストーリーを編まれております。
技術のみならずタネのクオリティも高く、少々お値段が行くコースですが、満足度は非常に高かった。
季節を表すタネとの出会いは、運と仕入れ次第なので、やはり真骨頂を味わうならば【おまかせ】だと思います。
(それでも他店に比べると良心的ですし!)
こちらの日本酒は品揃えが絞られており、
冷酒は1種類で佐賀県・窓乃梅、常温は高知県・菊水。
窓乃梅はスッキリした味わいで甘みがごく弱く、
苦味と香りが主張し過ぎずに底を支えているため、天麩羅を壊す事無く頂けました。
サイマキ(2尾)
一口で感銘を覚える素晴らしい火入れ。
レアな状態で旨味を活性化している。
あたかも肉におけるレアのように、中心部は半生だが熱を通し旨味を活かし、
甘みが非常に強く感じられる。
海老にレアな火入れを求める方ならば、親方を超えていると感じる仕事だろう。
サイマキ頭(2尾)
実に香ばしい。
頭までも柔らかな火入れで、外はカリッと仕上げつつ、
中には瑞々しさを内包している。
鱚
周囲の身は強く凝縮されつつも、中心部はほろりとほどける。
高温で長時間揚げ、過脱水寸前に迫る火入れ。
噛み締めてサクッと弾けた瞬間の香りは堪らない。
雄々しい鱚の仕事と言う印象。
当たり前だが、家では決して再現出来ない火入れである。
蕗の薹
食感の二重奏が面白く、ふんわり、とろっと段階的にほどける。
そして、香りは炸裂し、心地良い苦味が充満する。
大ぶりの蕗の薹の魅力を引き出す仕事。
海胆の大葉挟み
サクサクした大葉の衣を噛み締めると、じゅわトロッと海胆が滲み出る。
これは凄い揚げの技術!
好みを差し置いても、師匠を超える火入れである。
海胆は明礬の収斂味があるものの、甘みはしっかりしていた。
墨烏賊
ミディアムレアに仕上げ、墨烏賊らしい食感を活かす。
それでいて、スパッと切れる生の食感とは異なるため、鮨とは異なる魅力がある。
淡白な墨烏賊に衣の香ばしさが付加され、牽引する力を帯びる。
白魚
身の厚い白魚で、ふんわり、サクッと揚げている。
ラッキーにも子持ちの白魚も混じっており、季節の移ろいを愛でる事が出来た。
大きな魚体の魚だと子を持つと一気に魚味が落ちるが、
小さな魚体の魚の場合、影響が少なく、食感が増えるため嬉しく感じる。
タラの芽
強めに脱水し、香りと苦味を凝縮している。
これはこちらの流派ならではの匠の仕事。
虎河豚の白子
非常に上質な白子で、超濃厚。
舌にトロトロとまとわりつく粒子は官能的。
親方も「もう最後の最後」と仰るクオリティの白子で、
出会えたのは僥倖と言わざるを得ない。
メゴチ
特有の強い香りと旨味がしっかりと凝縮されている。
白子の後に出されるとは、嬉しい味わい。
非常に良い流れでメゴチを頂いた。
穴子
これは白眉。
走りの江戸前穴子であるが、産地を聞かずとも、頂けば分かる。
野趣溢れる香り、どことなく土っぽい香りは江戸前の証!
しかも、その個性が仕事によって引き立てられている。
身は必ずしも厚くないが、香りと旨味を十分に引き出している。
カリッ!ホロホロ!トロトロと三重奏を織りなす食感も秀逸。
力強さと繊細さを同居させた穴子である。
椎茸
香りがぶわっと広がり、食感は艶めかしい。
やはり職人さんの腕は野菜を頂けば明白。
サツマイモ
甘みと香りが凝縮されている。
甘いだけの一般的なサツマイモと大きく異なる。
茄子
全てに於いて衣と野菜の食感のコントラストが良い。
アスパラガス
繊維のほどけ方ととろけ方が凄いアスパラ。
甘みがジューシィに横溢する。
尚、師匠のお店では野菜は4種から2種を選ぶ選択性である為、
全て頂けるのは嬉しい。
お食事
かき揚げ丼と天茶を選べる。
タレと味わい、赤出汁を頂きたかったので、かき揚げ丼をセレクト。
香の物
赤出汁
大きめの蜆をたっぷりと用いている。
そして、しっとりとした火入れなので実に優しい味わい。
かき揚げ丼
これは師匠ともども最高の出来栄え。
柔らかな甘みが舌に広がり、小柱の香りがぶわっと鼻孔をくすぐる。
シャックシャクな身を噛み締めると、甘みが炸裂しタレと協奏する。
絶品である。
今度は江戸前穴子がピークになり、銀宝も出る初夏に伺おうと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:http://edomae-sushi.hatenablog.com/
9位
3回
2024/01訪問 2024/01/29
すしログ:香川を超えて江戸前鮨の可能性を広げる守破離の鮨職人!高松「鮨舳(すしとも)」
2015年9月に初めて訪問し、深い感銘を覚えた「鮨舳」さん。
当時は食べログのスコアは3.5でしたが、福岡の「さかい」さんと並ぶ、西日本を代表する鮨店だと確信しました。
その後、2016年8月、2017年7月に訪問しつつ、6年半の時を経て2024年1月に訪問。
結果として、標題のとおり香川県という土地を超えて素晴らしい試みをされている事に感銘を覚えました。
親方は江戸前鮨に真摯に向き合っておられ、同時に郷土寿司も再構築されている点が凄い。
東京のバブル鮨店がキャヴィアやトリュフなどを使って商売人へと堕ちる中、高松の佐藤親方は生粋の職人を貫いておられ粋そのものです。
克己の精神を感じます。
鮨職人の生きざまは顔や眼に表れる…と強く感じます。
「鮨舳」さんは写真撮影禁止なので、渾身の力を込めて魅力を表現します!
「すしログ」からフルで引用します…引用作業、大変だったーーー笑)
高松市「鮨舳(すしとも)」の魅力とは?
過去にお伺いした際には、「鮨舳」の佐藤 裕哉親方は地魚を駆使してご当地らしい江戸前鮨を構築されている点に感銘を覚えました。
江戸前仕事の巧みな応用が魅力だと。しかし、時を置いて再訪すると印象が変わりました。
より江戸前鮨の古い仕事に着目されて仕事を掘り下げておられる点が圧倒的だと気づいた次第です。
それは、以下の点で容易に気づくことが可能です。
店内に種札を掲げていて、仕込みの数が多い点
おまかせ一本ではなくアレンジして頂ける点
穴子の仕事が3種類あり、【爽煮】まで仕込んでいる点
おぼろも仕込んでいて、【おぼろ巻き】がある点
驚くべき事に【ひよこ】もある点
これは驚嘆に値します。
僕は終盤に【ひよこ】、【爽煮】、【おぼろ巻き】と頼みましたが、感動そのもの!!
今の東京で滅多に味わえない江戸前鮨の深い感動に浸りました。
この凄さを念のため説明すると、以下のとおりです。
各々の仕事の説明で、「鮨舳」佐藤親方の魅力もお伝えすることが出来るでしょう。
【ひよこ】の仕事
【ひよこ】は江戸前鮨初期の仕事で茹で卵を用いる変わり種の鮨ですが、今は無き京都の名店「松鮨」さんや人形町「㐂寿司」さんくらいしか出されていない、古典中の古典です。「㐂寿司」さんは創業こそ1923年(大正12年)と「新しめ」の老舗ですが、「與兵衞壽司」の流れを汲む現存店の一つです(残りもう一軒は創業1879年の日本橋「吉野鮨」さん)。「㐂寿司」さんでは「ひよっこ」と呼んでおり、これは江戸弁特有の訛りです。茹で卵の黄身の部分を抜き取り、黄身と海老おぼろを混ぜたものを詰めて握る、ユニークな鮨です。「㐂寿司」さんクラスの古典鮨を、高松の職人さんが表現されるとは…と驚嘆を覚えます。
【爽煮】の仕事
そして、【爽煮】について最も有名なお店は、言わずもがな浅草「弁天山美家古寿司」さんです。「弁天山美家古寿司」さんの創業は1866年(慶応2年)で、「鶴八」一門の原点のお店です(「弁天山美家古寿司」さんから出た柳橋「美家古寿司」の加藤博章親方は「江戸前鮨の神様」と呼ばれ、「鶴八」師岡幸夫親方を指導されました)。さらに言うと、「鶴八」一門の「しみづ」さんは現在の赤酢のシャリの塩梅に大きな影響を与えた職人さんであり、「しみづ」さん出身で活躍する職人さんは数多いらっしゃるので、江戸前鮨のメインストリームの一つの流派と言えます。【爽煮】に話を戻すと、これは穴子を真っ白に仕上げる仕事で、従来のようなメイラード反応を帯びた茶色系の煮方、漬け込み方ではありません。これまた、まさか香川県で出会うとは…と感じた次第ですが、むしろ産地ゆえに最適な仕事を選択されたのではないか?と感じました。その心は、現在の穴子の主流産地は対馬や韓国なので、脂が乗っていて、繊維質が柔らかいものが多いです。よって【爽煮】よりも現在主流の煮方がベターとなります。かつての江戸湾の羽田沖の穴子のようなものだからこそ、佐藤親方は【爽煮】を選択されたのではないかと感じたのです(職人に何でもかんでも尋ねるのは無粋なので、僕は推察する事も重視しており、理由を聞いていません)。つまり、江戸前仕事原理主義に陥らず、味を見極めて古い仕事を選択されているので、その点においてもセンスがあると感じる次第です。他者の調理法を全く同じ方法でコピペしたり濫用したりするのは三流。一流は取捨選択や換骨奪胎をしてナンボですね(これはビジネスにも言えますが)。
【おぼろ巻き】の仕事
最後に【おぼろ巻き】。
芝海老などのおぼろを仕込む職人さんが極端に減っているので、これは本当に素晴らしいことです。なにも古典を盲目的に礼賛しているわけではありません。おぼろ自体が抜群に美味しい江戸前の鮨種だから言っています。おぼろは昔のスタイルだと甘味が勝つ傾向にありますが、現代的に調整すれば素晴らしい種として昇華されます。海老の甘味や香りを楽しめるのは勿論、シャリの味を伝えてくれるのもおぼろの魅力。干瓢も素晴らしい巻種ですが、シャリの味わいをより鮮烈に伝えてくれるのは、おぼろだと思います。
さらに言ってしまうと、おぼろはおろか、巻物すら作れず手巻き一辺倒の職人さんも増えています。これは江戸前鮨の危機です。表層だけ見ていてはその料理の本質を知る事は不可能なので、本質的な古典にも向き合って頂きたいと感じます。鮨の一人前は握りと巻物によって構成されるものです。お金で買える油脂系の種や江戸前鮨としてはまがい物のキャヴィアやトリュフを揃えるのではなく、仕事が分かる種を仕込んで頂ければ、江戸前鮨がより楽しく発展していくでしょう。
僕は普段からそのように考えているため、高松で頂く佐藤親方の【おぼろ巻き】に江戸前鮨の深淵を見た次第です。期せずして訪問の直前に神保町「はる駒」にて田島親方の【おぼろ巻き】を頂いていたので、温故知新を強く実感しました(田島親方は前述の「鶴八」の暖簾を長く守っていた方です)。
佐藤親方の仕事の魅力とシャリについて
佐藤親方が用意されている種札の数は、なんとタネの数20枚、巻物の数3枚(他にも好みで巻いて頂けます)。質のみならず量もかね揃える仕事ぶりです。おまかせ一本で、追加の種を用意しない職人さんに見習って頂きたい仕事です。追加を聞いても、仕事をしていない赤鯥(ノドグロ)や黒鯥、金目鯛、甘鯛などでは実に味気がありません。おまかせを頂いた後に、これらを食べたいと思うお客は真の鮨食いではないでしょう。真の鮨食いが食べたいと思う仕込みをされる職人さんは、江戸前鮨業界の光だと断言できます。
しかも、佐藤親方は江戸前仕事の掘り下げだけでなく、郷土寿司のアレンジも行っておられる点が語弊無く感涙モノです。どのような寿司が登場したかは後ほど詳述しますが、僕が出会った中でもトップクラスにイノベーティブな鮨です。それを古典、伝統の温故知新を基に行っている点が実に崇高。「イノベーティブ」と聞くと、最新の調理技術や流行りの食材、提供方法などが頭に浮かぶかもしれませんが、伝統からインスパイアされる手法もイノベーティブである点はnomaが証明済みです。佐藤親方の試みは温故知新の革命と言えます。
なお、シャリについては、過去から変えられているようです(時が経っているので、そりゃそうですね)。お米は小粒が主体で、ぱらりとほどけ、温度は温かめ。塩気と酸味は上品で、お酢の熟成香がふんわりと漂います。メーカーを伺ったところ、ヨコ井「與兵衛」とミツカン「優選」のブレンドとの事でした。ちなみに、佐藤親方はもともと米酢のシャリと赤酢のシャリを2種類併用されていましたが、2018年以降に赤酢一本に絞られました。2種類併用時も共に完成度の高いシャリを切られていましたが、一本に絞られるとは実に硬派です。
「鮨舳」のおまかせコースの詳細
「鮨舳」さんは、厳密なおまかせコースを用意されているわけではなく、お客の好みに調整して提供されます。よって、僕が今回頂いたものが定型ではありません。ただ、ほぼフルで頂いたので、ご参考にして頂ければ幸いです。
オーダーについては、昔から多用しているフレーズ「酒肴については、握りで出されない、あるいは酒肴の方が最適な種を頂き、握り主体でお願いします」とお伝えしました。その後、追加を行っています。
2024年1月訪問時に頂いた内容
下記が2024年1月訪問時に頂いた内容です。
この度頂いたお酒
悦凱陣、石鎚純米吟醸、土佐しらぎく
鮃の刺身
当日の朝に締めた鮃。
もちろん弾力がありつつ、甘味と香りが込み上がる。
爽やかな味わいの鮃だ。
嬉しいことに三切れあるので、調味料なし、塩、醤油の順で頂くのが良い。
塩茹での蛸
切り付けのタイミングで香りが伝わる!
食感はしっとり柔らかく、さっくりと切れる。
煮ることよりも切り付けの厚みによって食感を表現出来る煮方だ。
蛸は旨味が強い。
実に旨いなー!と笑顔になった。
サッと火を入れたシラサ海老
観音寺市・伊吹島産。
標準和名はヨシエビ。
半透明に火を入れていて美しい断面!
もちろん味も良く、食感と甘味を引き出す火入れのバランスだ。
甘味が強くてプリプリ食感も楽しめる!
鰆の炙り
愛媛県産。
ガリのお酢で作った自家製ポン酢で頂く。
脂が乗り乗りで、香りも良し。
ポン酢は甘味と香りが良く、鰆の味を引き立てる。
牡蠣味噌と、鮟肝と奈良漬けのペースト
地物の牡蠣を用いた牡蠣味噌と北海道産の鮟肝。
牡蠣味噌は、香りと甘味が抜群で、ネガティブはゼロ。
鮟肝は提供方法が理に適っている。
共に調味の塩梅が良い。
ガリ
酸味がキリッと強めに効いていて、辛味がピリリと走る。
味を切る方向性のガリだ。
小鰭
名刺代わりの一貫目は小鰭!
赤酢でしっかりと〆た上で寝かせている。
それでいて、噛みしめるとしっとり感のある繊維質で、ジューシィさもある。
脂は強くないものの、江戸前の仕事で仕入れた小鰭を最大化させている。
これもネガティブな香りや味わいはゼロだ。
ハリイカ
墨烏賊=コウイカの西日本で使われる名前。
コリコリ感の後に甘味を感じさせつつとろりととろけてゆく。食感はゴリゴリまで行かず、コリコリ感で留まる。
赤貝
産地は伊吹島。
酢洗いで身を軽く収縮させている。
厚みがある赤貝なので、仕事が良い。
昆布様の香りは上品ながら、後から次第に込み上げてくる。
旨味だけでなく甘味が強い点が魅力的な味わいだ。
鯖と蕪の千枚漬け
小鯛笹漬と蕪の千枚漬けを用いる事が多い郷土寿司のアレンジだ。
実に素晴らしい試み!
部屋の温度で鯖の脂が滲むのが分かる。
頂くと、蕪の食感から鯖の脂と香りが活きてきて、これが赤酢に合う!
赤酢で作っている職人さんは他に出会った事が無いので、実に良い経験をさせて頂いた。
赤酢なので小鯛ではなく鯖に変えたのはジャスティスだ。
鯖のかぶら寿司
金沢を中心とする石川県の郷土寿司のアレンジだ。
しかも、残ったシャリに麹を用いて発酵させている点が崇高な志!!
発酵、熟成期間は2週間。
舌だけでなく喉で感じる複雑な味わいに魅了される。
麹による甘味がアシストしてくれる点も江戸前鮨に無い持ち味であり、提供の必然性を感じる。
そして、酢飯ベース故のサッパリ感がある。
なんて先端的!!!
鰤
部位ははらもで、仕事は漬け。
しかも10日との事!!
これは日数ではなく、選択する部位の必然性に感銘を覚えた次第。
皮目を残しつつ湯霜にして漬けている模様。
産地は長崎で、芥子を添えて。
実に理に適っている産地に対する仕事であり味わいだ。
文化圏外の食材をただ出すのでは凡庸であり疑問が残るが、自身にしか出来ない仕事を用いる試みがセンス抜群である証左
食感はプリプリしていて、脂のアタックは強すぎず、漬けと言う仕事の可能性を試している。
蛤
逆に蛤は漬け込みにより、しっかりな色合いだ。
いざ口に運んでみると、素晴らしい味わいで、まず香りが濃密!!
旨味もさる事ながら香りに魅了された。
漬け込みに伴う塩味や甘味も軽く、テクスチャーも軽やかでぷりっとしている。
味覚調整と仕事の見極めが実に良い。
鮪赤身
漁法は延縄で、仕事は漬け。
旨味があり、酸味も楽しませてくれる赤身だ。
噛みしめると香りが込み上げる。
鮪背トロ
持ち味の柔らかさが良い。
脂がありつつ酸味も効いていて、脂の甘味をスッキリと楽しませてくれるトロ。
牡蠣
頂く前から香りが良い。
テクスチャーとシャリの一体感が秀逸な仕事。
牡蠣味噌を噛ませて味わいの重層感もある。
海胆軍艦
小川。
海苔の香りも申し分無く、清涼感のある海胆だ。
甘味がありつつ、キリッとした後味。
穴子の爽煮
地物が入ったからとの談。
産地に関する仕事の選択理由は前述のとおりだ。
穴子はぷりっとしつつ、ホロホロとほどける。
これはこの仕事でしか味わえない楽しみ。
そして、本家の仕事よりも精度が高い。
15分ほどの火入れだそう。
焼き穴子
産地は韓国で、海苔を合わせる。
穴子の産地を使い分けて、仕事を選択されているのが素晴らしい。
脂が乗った韓国産の穴子を焼き込んで凝縮感を出し、海苔も炙ってから使用している。
味わいや香りのコントラストに妙がある。
椎茸の細巻き
意表を付く巻物だが、関西を中心とする椎茸の仕事を応用している。
こっくりと甘く味付けを行い、コリッとした食感に炊いている。
木ノ芽を用いる点も関西酢の定番の仕事だ。
玉子
卵黄の色が濃い卵を使用されていて、オレンジに近い見た目だ。
そして、中心部はとろりと軽い火入れで、二重構造になっている。
ひよこ
黄身酢おぼろではなく玉子おぼろを使用!
出会えて嬉しかったのは上述の通り…。
白身の冷たさから黄身の甘味が広がり…終盤に良いなあとしみじみ。
卵に切り込みを入れている点は親方のアレンジ!
良いと思う!
おぼろ巻き
最後におぼろ巻きで〆る幸福を高松で頂けるとは感慨無量である。
過去に何回か伺い、西日本の若手職人さんだと有数の腕を持つと思うお店です。
この度、初めて7月に訪問しました。
訪問当初は食べログで3.5ほどだったので、
ここのところのスコア高騰には驚くばかり。
また、敢え無く写真撮影不可になってしまいましたが、
その分集中して頂けるのは嬉しいと考えましょうか(笑)
再訪して、矢張り相当の実力をお持ちな職人さんであり、
今後の可能性を感じさせて頂きました。
この度頂いた日本酒。
土佐しらぎく、船中八策、勇心、石鎚。
今回は酒肴は3品のみ。
握り主体で頂きました。
真子鰈
肉厚!極めてぶりぶりな食感で、強い甘み。
個人的に大変好みの白身の寝かせ方。
旨味と香りもバッチリであり、3日以上寝かせて食感がダレたものとは異なる。
蛸
地もの。3分のみ茹でたとの事。
蛸としては大変短い火入れだが、噛み締める喜びがある。
噛むごとに香りが高まる。
今や鮨店で定番中の定番となった【桜煮(柔らか煮)】とは異なる魅力。
蛤
桑名の蛤。
身はトロトロで、煮ツメが良い仕事。
蛤の苦味と旨味に寄り添い、異なる旨味で引き立てる。
この後、握りに移行します。
タネの後に記載している(白)、(赤)は使用する酢の違いとなります。
合わせたワインではありません(笑)
真子鰈(白)
昆布〆。最初に鰈の旨味が来て、ねっちりした食感と共に昆布由来のグルタミン酸が感じられる。
酢の酸味との相乗効果が良く、理に適った昆布〆。
最初の一貫として、穏やかに盛り上げてくれる。
剣先烏賊(白)
肉厚な烏賊に超細の包丁を入れている。
徹底的にトロトロした食感を演出しており、甘い!
蝦蛄(赤)
大ぶりの子持ち蝦蛄で、思わず「おおっ」と声が漏れる。
しっかりと漬け込んでおり、煮ツメで提供。
淡白な2貫の後に面白い流れ。
卵の含有量が多く、細かくプチプチと弾ける。
小鰭(白)
しっかり目に〆ているが、しっとり感もあって美味。
酢の浸透も強めだが、小鰭の香りがふつふつと立ち上がる。
鮑(赤)
蒸した鮑に肝を噛ませている。
切り付けが面白く、厚みのある部分と薄い部分があり、波を打たせている。
香りが抜群で、柔らかな身からゼラチン質がたっぷりと滲み出て、
旨味に流されそうになったところで、肝の苦味と風味が味わいを調整する。
緩急の付いた味わいである。
赤酢のシャリとの味覚的なバランスも良好。
味わいが良いので産地を伺ったところ、小豆島産との事。
鯵(白)
超大ぶりの鯵を半身使用。
叩いた青ネギを噛ませている。
シャリの酸味との相乗効果がこれまた高く、旨い。
塩2分、酢2分で〆ているそう。
ノドグロ(赤)
炙っているが、ほぼ皮目だけの炙りで、身は生。
身の旨味を活性化させつつ、生の魅力も楽しめる。
エゾイシカゲガイ(赤)
エゾイシカゲガイ(イシガキガイ)は都内でも頻繁に用いられるようになっているが、
全てが全て美味しいと言う訳ではなく、
仕入れのセンスも要求される状況にあると感じる。
蔵前の幸鮓さんは早い段階から使用されていた。
マナガツオ(赤)
炙って皮をパリパリに仕上げ、皮が弾けるや否や旨味が横溢。
赤酢のシャリと香ばしさ、脂の旨味が良く合う。
真鯛(白)
後半戦に真鯛とは、面白い流れ。
香りが強く、旨味は上品。
2キロ弱との事で、瀬戸内の鯛は夏にもう少し旨味を増す。
鮪赤身(赤)
20秒くらいの短い漬け。
爽やかな鉄分を楽しめる。
煮キリを変えておられ、たまり醤油的なコクが奏功している。
鮪中トロ(赤)
サラッとした旨味だが、脂はシャリの酸味と結合し魅力を増す。
海胆(白)
由良の赤海胆で、形が非常に綺麗。
冷えているのに一瞬で溶け去り、ただただ旨味が残る。
ミョウバン入りの海胆は室温で馴染ませる必要があるが、
上質な塩水海胆は低い温度帯でも口どけが良く、旨味を瞬時に感じられる。
鰯(白)
ひたすら、トロトロトロトロ。
抜群の脂の旨味。
〆加減が素晴らしい。
叩いた青葱と生姜を噛ませている。
焼き穴子(赤)
煮穴子(赤)
穴子を東西2通りの調理法で供されるのは、大変面白い。
香りが炸裂し、煮穴子はトロトロ。
焼きで食感と香りを楽しんだ後に、煮穴子で甘みを楽しむ。
玉子
車海老とマナガツオを使用した贅沢な玉子。
大変味わい深い。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
前回、お昼に伺って感銘を覚えた鮨舳さん。
この度、夜に訪問してみました。
酒肴を少し、握り中心で頂いたところ、以前に抱いた感動は色褪せず。
むしろご主人の完成度の高い仕事に惚れなおす事となりました。
東京には「酒肴を少し」と伝えているのにバンバン出してくる職人さんがいますが、
あくまでも握り主体で満足感を与えてくれるのが素晴らしい。
しかも、驚いた事に、お好みにも対応されておりました。
満席だと言うのによくぞ…と東京で失われつつある江戸前鮨職人の魂を、香川の地で感じました。
頂いた酒肴は三品となります。
マナガツオ
昆布で〆たお造り。
香川の東側で獲れたものとの事。
焼きよりも香りと甘みがストレートに感じられ、一品目から驚き。
生の刺し身ではなく、仕事を施した刺し身を出されるところにもグッと来る。
昆布のグルタミン酸もマナガツオとのバランスが良く、かなり良い〆!
黒鮑
小豆島産。
圧倒的な香りと旨味で、一口一口ごとに前の味わいを超えてくる。
ひとえに仕事によるもの。
肝は雑味が少なく海藻を彷彿させる爽やかな香りが心地良く、苦味が極めて柔らかい。
鰻
岡山市旭川産。
力強い香りと強い甘みを楽しませてくれる鰻。
素晴らしい火入れで、身はふっくら柔らかくジューシィで、
皮はパリパリと軽やかに弾ける。
タレは甘みを利かせているが、全く嫌みが無く、
あくまでも素材が勝つ。
この後、握りに移行します。
アマテガレイ
江戸前で言う、真子鰈。
力強い食感の身を噛み締めると、香りと旨味が横溢する。
そして、シャリとの相性も素晴らしい。
一日弱寝かしているようだが、食感、香り、旨味の三拍子が揃っていた。
マメアジ
切り身を三枚付けに。
しっかり〆ており、噛み締めると旨味が弾け出る。
下処理、仕事ともに秀逸。
鯵
これも〆加減はしっかり。
下北沢の小笹寿しが生み出した葱と生姜を叩いた薬味を噛ます。
〆の仕事により旨味が凝縮されており、薬味と一体となって、鮮烈な味わい。
鯵の清々しい香りも鼻を抜け、夏の海を髣髴とさせる。
剣先烏賊
これは素晴らしい包丁。
僕は烏賊は墨烏賊にしても包丁を楽しむタネだと考えているが、
ご主人の包丁は食感を計算されており、歯切れが抜群。
歯応えと柔らかな歯切れが相まって、食感の奥から身を現す甘みが甘美。
シズ
標準和名イボダイで、東京ではエボダイ、隣の徳島県ではボウゼとも。
ご主人お得意の酢橘〆。
抑制が利いた酢橘の香りが、やはり上品。
マナガツオ
こちらは赤酢のシャリで。
皮目がサラリと消えるように溶けた後、甘みが口腔を満たす。
炙り加減が奏功している。
クロメ入りの藻塩も塩気が尖っておらず、ミネラル分が多く旨い。
ちゃりこ
いわゆる春子。
うーん、素晴らしい。
〆により甘みが凝縮されており、食感はしっとり。
イシガキガイ
これは岩手産との事。
磯の香りがとても良く、甘みが圧巻。
シャクシャクと気持ち良い身を噛み締める度に魅力を感じる。
赤酢のシャリが貝に足りない部分を補い、相乗効果を生み出している。
鮪赤身
軽く漬けにしており、酸味が心地良い。
噴火湾の30kgのものと、小さい魚体。
鮪トロ
これは圧巻。
鮪の甘み、シャリの旨味、煮キリの塩気のバランスが絶妙で、
夏場の鮪の魅力を完全に引きだしている。
完全にご主人のセンスによって活性化された鮪。
小鰭
味はしっかり〆ていたが、小鰭はしっとり目の〆加減。
香りと旨味を引き立てており、小鰭の時期を計算した仕事だと感じる。
余韻が極めて長く、夏の小鰭とは思えない仕事ぶりに青空で頂いた小鰭を思い出す。
剣先烏賊
愛媛県産。ここで煮烏賊とは!
煮ておりながらパツパツとした食感が魅力的。
山葵を多めに使用し、濃厚な煮ツメとの塩梅が良い。
ここで、次のお客さんの分のシャリを切られ、驚き。
ここまで徹底している江戸前鮨店は稀有だ!
車海老
地物を茹で上げで。
繊細に包丁を入れ、丁寧に背肝を処理されたのが印象に残る。
しかし、言葉を失うほどに素晴らしい火入れ!
柔らかく仕上げ、シャリと調和する温度に調整してから握っておられ、
甘みの伝達が圧倒的。
ここまでの海老の仕事を出来る職人は、日本に何人いるだろうか?
鰯
北海道産。脂が乗っているため、酢を強めに入れて〆ており、トロトロな食感。
これだけ、少し残念ながら、最後に鰯の嫌な部分の香りがかすかに漂ったが、
恐らく感知出来る人は少ないレヴェルかと(僕は嗅覚が強いので…笑)。
赤雲丹
淡路産。舌に乗せた瞬間にとろけ、官能的な甘みと香りが!!
このクオリティは凄まじい。
今年頂いた淡路の赤雲丹ではトップレヴェル。
赤雲丹
愛媛県大島産。ねっとりした甘みの後にシャープな香りが一閃…
この針葉樹ないし松を思わせるキレのある香りは紛れも無く、
今治〜松山あたりの雲丹の特徴。
淡路の赤雲丹とは全く異なる面白さがある。
いやあ、コレは嬉しい食べ比べだった。
穴子
トロトロと消え去る。
濃厚な煮ツメとのバランスも長けている。
一言、旨い。
香川県牟礼の穴子との事だが、希少性が非常に高く、
今年は10本ほどしか手に入っていないとの談。
玉子
車海老以外に複雑な旨味を感じたので、伺ったところ、
マナガツオも混ぜているとの事。
そして、山芋に加えて使用する砂糖は和三盆。
香り、食感の両方が秀逸な玉子。
以上、酒肴3品、握り18貫、玉子、日本酒3号を頂き、19,000円弱。
頂いた日本酒は、【悦凱陣 純米吟醸ブルー 山田錦】、
【勇心 純米 おいでまい】、【悦凱陣 純米 阿州山田錦】。
コストパフォーマンスの高さよりも、
握りの技術の高さと仕事の完成度に感服しました。
また機会を作って訪問したいと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:http://edomae-sushi.hatenablog.com/
【2015年9月】
若手ながらに香川で注目を浴びている職人さんがいる…と聞いて、
かなり期待して訪問しました。
それと言うのも、ネットで見る握りの写真が端正だったので。
しかし、伺ってみて、期待を遥かに超える満足度で、驚嘆を覚えました。
まず素晴らしいのが、店内の香り。
実は、都内の高級店でも香りに乱れがあるお店はザラにありますが、
こちらは清浄な空気に酢の香りが滲み、大変気持ち良い。
次に素晴らしいのは、お茶の差し替えのタイミング。
こちらほど正確にお茶を替えられるお店を、僕は他に知りません。
さりげなく、きめ細かい。
特に、強い味わいのタネの後、確実に新しいお茶に替えて頂けるのは気持ちが良かった。
そして、肝心の握りの方も面白い。
シャリは、前半は米酢のもの、後半は赤酢のものと使い分けられるのですが、
違和感無く、両方のシャリの完成度が高い。
2つのシャリを使われて違和感が無いお店は少ない。
ご主人の握りは精確で、捨てシャリをする事は無く、
手元に乱れがありませんでした。
仕事の方も瀬戸内の素材を江戸前の枠組みで解釈されており、
独自の世界観を提示してくれます。
なお、シャリは口に入れるや否や鳳仙花の如く米が弾ける。
硬めに炊き上げ、握り加減が良い。
味付け的には、酢がやや強めで、現代的な味わいです。
赤酢のシャリの方は、ヨコ井の酢を使用されているそうです。
最後に、山葵の管理も良かった。
こまめにすりおろされ、乾かぬよう慎重に皿を返す。
…とどのつまり、全てにおいて「もてなしの心」が顕れた稀有な鮨店だと感じました。
ガリ
甘みが無くスッキリした味わい。
真鯛
歯応えがあり、香りが強く、抜群の甘みを楽しめる。
一貫目で確信を覚えるタネのクオリティ。
アイナメ
昆布で〆ているが、塩梅が良い。
昆布の香りと旨味を移し過ぎず、アイナメの魅力を高めている。
エボダイ
珍しい、酢橘〆。
酢橘は抑制が利いており、上品な香りを残す。
ハリイカ
江戸で言う墨烏賊。
厚みのある切り付けだが、歯切れは良く、甘みたっぷり。
鮃(ヒラメ)
昆布〆だが、鮃の香りは非常に強い。
聞けば青森産との事。
噛みしめると滲む甘みは鰈とは異なり、季節の移ろいを感じる。
鮪赤身
漬け時間は1分程度(計りましたw)。
ここから赤酢のシャリに変わります。
産地は大間ですが、特にこだわりは無く、一番美味しいと思うものを使うとの事。
甘みの引き立て方が巧く、食感はねっちり、シャリとの相性が抜群。
小鯵
小鯵とは珍しい。程良い酢加減で〆ており、合わせた調味料が良い。
葱とすりおろした生姜をペースト状にしたもの。
ミル貝
ミル貝も赤酢とは驚いたが、甘みを引き立てている。
イクラ
浅い漬け加減で、粒たちは爽やかに溶ける。
上品な口当たりと広がりのある余韻。
カマス
炙ってあり、とにかく懐かしい香り。
鯖
脂、香り共に中々時期を考慮してか〆加減は弱めで良い。
鰆(サワラ)
漬け。甘めの煮キリを使用しており、面白い。
鮪中トロ
温度の戻し加減が良い。
小鰭
皮目の食感は瑞々しく、酢をそれなりに用いつつ香りを活かしている。
シャリは米酢の方で。
蛤
煮ツメは濃い口でタイプ。
赤海胆
淡路産で、訪問の翌日から禁漁になるとの事でラッキー…
苦味が無く非常に美味しい。
真鯛のあら汁
海老
茹で上げ。肉厚ながらに甘みを活かす良い火入れ。
鰆(サワラ)
今度は軽く炙ったもので、皮はとろとろ、脂が滲む。
穴子
ふんわり柔らかな仕上げ。
玉子
良質の練り物のような食感。甘く無い。
トータルで19貫(+椀、玉子)なので、お会計を待つ間、「覚悟」しておりました。
しかし、お会計は14,000円。
タネのクオリティを考慮すると圧倒的なコストパフォーマンスです。
味わい、サーヴィスを兼ね揃えた名店である事は間違いありません。
全国で鮨を食べておりますが、個人的に三ツ星クラスの地方江戸前鮨店かと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
10位
2回
2018/10訪問 2021/05/05
以前お伺いした時から、再訪を楽しみにしていたコチラ。
前回は初夏の訪問でしたが、今回は秋に訪問致しました。
頂いた感想としては、矢張り独特のセンスが光る内容であり、
滋賀らしさを懐石の枠組に落とし込む事に成功していると再認識しました。
僕は常々、郷土料理が廃れる危惧を抱いております。
昔通りの郷土料理も大変魅力的ですが、
廃れないため、多くの現代人の琴線に触れるためには、
モダンな感性でちょっとしたアレンジを加える事が必要です。
そう言った意味では、ご主人・瀬海悠一朗さんの存在は滋賀県において貴重であり、
普段モダンな日本料理を食べている人にも響く(であろう)御料理だと感じました。
この度頂いた御料理(1万円)
・先付:柿の柿和え
・イサザの天麩羅
・「握らない鮨」2種
・お造り:鰹、鯛
・椀:鱧と白舞茸
・子持ち鮎の炊いたん
・炊き合わせ:銀杏真薯、鱧、松茸、里芋
・近江牛ミスジの焼きもの、信長味噌
・お食事:栗ご飯、香の物、留め椀
・水菓子:いちじく、シャインマスカット、葡萄のシャーベット
先付
「柿の柿和え」と言う面白い料理名。
熟成期間の異なる柿を、焼きと餡の2通りの調理法で組み合わせている。
これは素晴らしい味わい。
濃密な甘みの餡が焼き柿の輪郭を強める…
香ばしさに加えて酸味が引き立っており、
柿を柿に対して調味料的に用いた素敵な一品。
イサザの天麩羅
琵琶湖固有種のハゼであるイサザ。
今シーズン初物との事。
ハゼ科特有の力強い風味に、ホロリと溶ける繊維質が美味。
握らない鮨
伊勢神宮の御神米(神に捧げるお米)であるイセヒカリを用い、
赤酢の酸味を付け、甘みも加えた酢飯。
一品目はウロリ(ヨシノボリ)。
ウロリは滋賀で甘辛く炊く事が多い郷土佃煮。
それを酢飯で上品にアレンジしている。
続いて二品目は、炙り鮒鮓。、
香ばしさに加えて脂が活性化しており、
これは大変素晴らしい!
鮒鮓らしい酸味が底を支えつつ、
生の状態よりもごく弱い酸味になっており、
酢飯とのバランスが良好。
お造り
登場した時には滋賀で戻り鰹!?と思うも、脂が乗っており、
何よりも燻し加減が上手い!
付け合わせの醤油はコクが非常に強い。
なお、器は白井半七(の写し?)。
鯛薄造り
滋賀県湖南の伝統野菜・弥平とうがらしを散らせて。
鯛は旨味が乗っており、熟成を掛けている模様。
そこに唐辛子のピリッとした辛味が良い小技。
ポン酢は出汁が美味しい。
唐辛子は単体で噛みしめると結構辛味があり、香りも強い。
椀
鱧と白舞茸。
鱧は肉厚でぷりぷり、旨味もしっかり。
割と力強い吸い地だが、
白舞茸とミョウガがたっぷりなので一緒に頂くとピッタリと合う。
子持ち鮎の炊いたん
極太!これは滋賀らしく、
甘みを付けた炊き加減(甘みは伝統的なものよりは相当軽い)。
ひたすらプチプチと弾ける卵が気持ち良い。
器は尾形乾山(の写し?)。
炊き合わせ
銀杏真薯、鱧、松茸、里芋
銀杏真薯はねっちりした銀杏が堪らない。
キレのある美味しい出汁に松茸の香りが滲む。
近江牛ミスジの焼きもの、信長味噌
信長味噌は豆味噌で、中国の豆豉的なフレイバーがある。
安土養蜂園の蜂蜜をブレンドしており、大変美味しい調味料。
山葵との相性も抜群。
勿論、牛肉自体の旨味、火入れも申し分なし。
お食事:栗ご飯、香の物、留め椀
お米自体がかなり美味しい!
お世辞を抜きにして、瀬海さんは日本でも有数のお米を炊く腕だと感じた(笑)
粒が凛々しく存在感を放つ!
抜群の食感に加えて、甘みも印象深い。
炊きの技術によって、お米の魅力を引き出している。
古来からお米の名産地である滋賀の強さを感じさせてくれる。
イサザの佃煮、味噌汁、香の物もバッチリ美味しい。
最後になってしまったが、栗の甘みに癒され、大満足(笑)
水菓子
いちじく、シャインマスカット、葡萄のシャーベット。
シャインマスカットは最近大人気を博す品種だが、
葡萄のシャーベットも負けじと濃厚で美味!
またお伺いする日を楽しみにしております。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
こちらはかつて織田信長の城下町であった安土に在る、
1911年(明治44年)創業の老舗料理店です。
元々は仕出しメインのお店でしたが、
現在のご主人の代で懐石料理も供するようになった模様。
まだお若いご主人は創業101年目を迎える際に大阪の修行先から戻り、
生産者や陶芸家さんとの交流からインスピレーションを得つつ、
オリジナリティ溢れる料理を作られております。
伝統的な郷土料理にモダンな感性を交えた御料理は此処でしか頂けないものばかり。
「滋賀らしさ」を組み込み、その日その日の食材でコースを編んでおられます。
現状、食べログでスコアが付いておりませんが、ご主人のセンスは唯一無二です。
お店は完全予約制で、基本的には4人以上が必要。
それ以下の場合は、コース内容を含めてお電話にてご相談されてください。
頂ける食材は訪問する日の「食運」次第となりますが、
逆に、アドリブが利いた料理はこちらの魅力の一つだと感じました。
お部屋に通された後に頂いたお茶は大変旨く、
称賛したところ、雁ヶ音の茎茶を使用されているとの事でした。
お茶の美味しい日本料理店は外す事が少ない気がします。
頂いた料理は下記の通りです。
鮎鮓
滋賀の伝統鮓である【め鮓】をアレンジした一品。
伺ったところ元々は「ハイを用いる鮓」との事なので、
標準和名オイカワを用いた発酵料理(ナレズシ)だと推察する。
ハイを使用する場合は3日間発酵させるそうで、タイミングが良ければこちらでも頂けるとの事。
小魚で作る鮓ゆえに一度に大量に作る必要性がある為、出会えるか否かは正に食運次第だ。
しかしながら、この度の小鮎を酢で〆て作った「早熟れ」の鮓も一興。
「早熟れ」なのでサッパリとした味わいで、微塵切りの紫蘇を噛ませ、
すりおろした生姜を合わせ、夏らしい爽快感を演出した先付に。
使用するお米は酒造好適米のイセヒカリ。
甘みを付加し、全体的なバランスを取っている。
ハイを用いた伝統的な鮓も気になるが、
伝統料理をアレンジした秀逸な品であると一品目から感嘆した次第である。
天然琵琶鱒の冷燻製
頂けるかな…と期待を頂きつつ訪問した為、出会えて嬉しかった琵琶鱒。
山中塗りの皿の上で陽光を浴び、あたかも泳いでいるような盛り付け。
冷燻なので火を通さずにあくまでも軽い燻蒸香を付ける仕事であり、
塩気は強めだが、燻製で身は引き締まり旨味が凝縮されている。
琵琶鱒の香りと旨味を楽しませてくれる。
琵琶鱒の筋子が調味料となる。
そして、酢飯と合わせている点も嬉しい。
先付からお米が続くが、ご主人がお米好きとの理由(笑)
完全に同意するところ。
真鯛の皮霜造り
2kgの真鯛を熟成したもの。
熟成の塩梅は中々良く、練られた旨味に炭火での焼き霜が興を添える。
山葵は辛味が低く甘みの強いものを使用し、
醤油はたまり的な味わいを持つ土佐醤油をベースに甘みを立てたもの。
器は尾形乾山のカキツバタの茶碗の写しである模様。
焼き茄子とイチジクの利休餡
上記の渋い流れに投じられる、清涼感と美しさに溢れる一皿!
調理法、器ともに実に良い展開である。
しかも、味覚的調和が極めて高い。
焼き茄子の香り、イチジクの甘みに利休餡が絡まり、
ジュレの旨味が全てを接続する。
ジュレは今や日本料理で多用される存在だが、
こちらのジュレは鰹と昆布を用い、口当たりは硬めで個性を有す。
利休餡は胡麻の風味がしっかりしており、甘みと塩味が全体のバランスを取る。
ひたすら爽やかな味わいだが、胡麻のフレイバーが牽引し、
ジュレの旨味が底を支える、実に奥深い味わいであった。
尚、清涼感溢れるガラスの器は竹中悠記さんのもの。
天然鰻の焼きもの
琵琶湖に浮かぶ沖島近くで揚がった鰻。石臼挽きの山椒と木の芽を添えて。
地焼で焼き上げ、照り焼きよりも飴焼きに近い仕上げ。
身はホロホロで、旨味は厚みを考慮すると強いと言える。
皮は照り照り、パリパリに焼き上げており、これ自体が良き酒肴である。
嫌味無い鰻の皮の香りも心地良い。
鯉の筒煮
なんとここで子持ちの鯉の豪快な料理が投入される。
味付けは甘みが強めだが、身には浸透させておらず、
このあたりに伝統料理の現代的なアレンジを感じさせる。
生姜の細切りにご主人の包丁の腕を感じ、強い味付けながらに魅力的な一品。
器が気になったので伺ったところ、
近江八幡のビストロだもん亭で腕を振るうアメリカ人料理人の作との事。
また行きたいお店が増えた。
冷やし茶碗蒸し
安土・大中(だいなか)産の玉蜀黍(とうもろこし)のすり流しに葛を打った餡を添えている。
頂いてみると葛はほんの少しの使用量で、嫌味が無い。
具は椎茸と空豆で、卵の風味もしっかりと感じ、素材が良い事が分かる。
薬味の周りに軽くゲランドの塩を振っている点にもグッと来た。
近江牛のミスジと白茄子
こちらの構成で近江牛が出ると、ついつい頬が緩んでしまった。
極めて必然性のある日本料理おける牛肉の使用法だと感じる。
肉はぷるぷる、パツンと弾け、脂は舌に媚を売らない程度の甘み。
出汁に柚子胡椒を溶いて葛打ちした餡も味わいを引き締める。
器は小川顕三さんの信楽焼の片口。
琵琶鱒ご飯
冷燻でも喜びを覚えた琵琶鱒アゲイン!
琵琶鱒の香りが実に!!素晴らしい!
そして、琵琶鱒らしい旨味が出ており、それを活かす上品な味付けも見事。
土鍋は言わずと知れた中川一辺陶さんの雲井窯。
味噌汁は発酵感が強く甘みのある味噌を使用。
水菓子
マンゴー。本来ならば貴重な琵琶湖産のマンゴーを出したかったそうだが、今回は宮崎産。
ジュレは白ワインを湧水で割ったもの。
デザートもセンスが光る調和に満ちた一品だった。
おまけでレア種無しマンゴーも頂きました。
次回は秋もしくは冬にお伺いしたいと思います。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
今までは夏の訪問ばかりだったので、今回は自身初の冬訪問となります。
冬の魚の旨味がピークとなる時期に狙いを定めて訪問しました。
現在はお昼も営業されており、なんと1日3回転となっております。
しかも、お昼も夜と同じ内容との事で、濃密極まりないです(笑)
ただ、1日当たりの負荷を増やしつつ、お休みを連休にされるなど、
既存の飲食業界を考慮するとホワイトな試みをされている点に、
堺大悟親方の職人気質だけでなく優しいお人柄を感じます。
ワークライフバランスを確立するレストランが増えておりますが、
そうでなければならないと感じる次第です。
多くのお客はいつでも美味しいものを頂けるのが当たり前だと考えがちですが、
料理人の方が心身ともに充実してこその美食だと思いますので…
ちなみに、営業時間を延ばすと共におまかせの価格も変更されておりました。
以前はお酒を飲んで24,000円ほどだったところ、現在は33,000円ほど。
「値上がり」となりますが、酒肴のラインナップと仕入れが強化されておりました。
3万円オーバーのお店は人によって評価が大きく変わる可能性がありますが、
堺さんの握りはそれでも人を惹きつける圧倒的な力があると再認識しました。
頻繁にお伺い出来る価格帯ではなくなりましたが、
必ず再訪したいと感じさせる、説得力のある味わいです。
そして、改めて堺さんの赤酢のシャリは美味しく、
タネとの相性を考え尽くされた味付けだと感じました。
以前よりも酸味を少し利かせているように感じましたが、旨味が引き出されたタネと馴染み、
力強さを持ちながら、端正であり上品でもあるシャリだと感じた次第です。
温度管理や硬さは申し分ありません。
この度頂いた日本酒
白糸酒造・シライト35純米大吟醸、木屋正酒造・而今特別純米、
福禄寿酒造・一白水成純米吟醸、西田酒造店・田酒特別純米
鮨さかいさんの酒肴
ノレソレ(穴子の稚魚)
甘酢をダイレクトに用いるとノレソレの風味が死ぬため、
甘酢をジュレにして提供されている。
出汁と甘みの利かせ方が良い。
子ヤリイカ
糸島産。食感と歯切れが良く、柔らかくほどける。
九絵
対馬産の10キロ。1週間熟成。
堺さんの熟成仕事は香りを重視されている。
野趣ある香りが立ち込め、非常に強い旨味がほとばしる。
毛蟹
北海道・噴火湾産。間違いない美味しさ。
鱈の白子
根室産。現地で言うところの「タチポン」。
と思いきや、ポン酢ではなく出汁で和えておられる。
よって、白子の甘みをより強く感じる。
虎河豚
福岡産の虎河豚に島根産のカワハギの肝酢を乗せた酒肴。
実に素晴らしい味わい!
「オープン以来、一番人気のおつまみ」との事。
濃厚ながらスッキリしたニュアンスのある調理。
肝酢は乳化状態にあり、言わずもがなで濃密な旨味があるが、
2日寝かせたフグはそれにも負けない旨味と香り。
異なる魚の身と肝を合わせるのは日本料理的には少し飛び道具であるが、
バランスが取れているため非凡な完成度である。
黒鮑
唐津産で、師走に解禁されたそう。
まだまだ走りと言えども香りが官能的で、旨味もあるある。
思わず、翌日平戸漁港で入手して自分も調理した程(笑)
鮟肝
産地は定番とも言える余市であり、堺さんが「一番美味しい」と考える。
出汁が奏功しており、甘みは抑え目。
鮟肝自体、鮨店の酒肴の定番中の定番だが、モノの味をストレートに表現した鮟肝である。
虎河豚の白子焼き
鰹出汁の銀餡と共に。
濃密で香り良く、冬の喜びを体感。
ノドグロ(アカムツ)の味噌漬け
これも裏切らない味わい。
この後、握りに移行します。
鮨さかいさんの握り
アオリイカ
呼子産、2日寝かせ。
浅い包丁が活きており、アオリであるが甘みの前に食感を楽しませる仕事。
針魚
小柴産の閂(カンヌキ)サイズ。
食感を楽しませつつ、柔らかなのは包丁故。
メジマグロ
佐渡島産の15キロ、漬け。
味わいが大変面白いタネ。
酸味に加えて脂がふつふつと込み上げるような味わいは、
成体の本鮪にはない楽しみ。
部位は腹側。
小鰭
〆て2日寝かせ。
みっちりながら柔らかな印象を与える小鰭であり、シャリとの相性も良い。
鮪の産地は宮崎県・油津との事で珍しい。
魚体は144キロで、漁法は延縄。
10日ほど寝かせている。
鮪赤身
甘みが強い赤身。
温度の戻し方が絶妙。
鮪中トロ
噛みしめると脂がどんどん高まるが、下卑た感じた皆無。
鮪大トロ
これのみ漬けていない。
筋っぽい見た目とは裏腹に、とろっとろ!
ボタンエビ
増毛産。卵を噛ませて、表面のみ漬け(煮キリを塗り置く)。
表面は程良く凝縮しており、中はトロトロ。
卵の食感は全く気にならず、一体感が非常に高い。
べったら漬け
蛤
九十九里産。
噛みしめる喜びのある火入れ。
噛めば旨味と香りが高まり、シャリの酸味が活き、味を引き締める。
海胆
一大ブランド・はだてのキタムラサキ海胆。
一瞬、粒感を舌に感じさせつつ、とろける海胆。
海胆軍艦
走りの唐津産ムラサキウニ。
香りが鋭い点が印象的で、喉に香りと旨味が残る海胆。
旬モノに比べると弱いため、海苔を用いておられる。
椀
ボタンエビの頭の出汁の味噌汁。
磯の香りが横溢する。
味噌の使い方が上品。
穴子
本当にトロトロで、飲み物のような穴子。
甘み強いが、野趣ある香りも残る。
対馬産(恐らく)としては強い風味が好印象。
鉄火巻
玉子
またお伺いする日を楽しみにしております!
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/
その後、お店を移転されたと聞き、楽しみに再訪しました。
お店は前よりも広くなり、キリッと爽やかな空気が漂い、心地良いです。
天井高もあるため、かつての「洞窟感」は無くなり、開放感がアップしました。
再訪した感想としては、改めて「西の雄」と言う印象を強めました。
シャリが美味しく、仕事と握りの精度も抜群に高い上、
ストーリー性(構成力)、温度帯のコントロールなども秀逸。
個人的に、赤酢を用いた握りだと西日本一だと感じます(全国でもトップクラス)。
赤酢主体でありながら酸味は比較的穏やかで、塩気やや高め、
硬め、少しだけ温かめなシャリは、一口一口に喜びがあります。
頂いた日本酒
而今・特別純米火入れ、東洋美人・ippo山田錦、綿屋・純吟阿波山田錦、
握りに合わせて田酒・特別純米、日高見・弥彦。
蛸の柔らか煮
五島産。包丁を入れられた瞬間を見て、柔らかさが伝わってきた。
実際に頂いてみるとトロトロな皮が兎に角旨い。
そして、香りも良い。
山葵は鼻に抜ける辛さで、爽やか。
御殿場産を使用しているとの事。
九絵とヨコワ
4キロ、西日本の夏を代表する白身魚・キジハタ(アコウ)に比べると、
力強い食感と力強い香りが魅力。
やや血を感じさせる雄々しさがあり、旨味は強く、余韻にも妙あり。
ヨコワ(クロマグロの子ども)は8キロのものを藁で炙って。
皮下脂肪が凄いため、藁の火入れが奏功している。
当初、燻蒸香が強めかと思ったが、噛み締めると魚味と協奏し良い塩梅。
尚、煎り酒は軽い甘みと梅のとろみが特徴的であった。
増毛のボタン海老、唐津の赤海胆
実に嬉しい共演、土佐酢のジュレで。
土佐酢に加えて、酢橘の皮が爽やかな香り。
ボタン海老のとろろんとした媚態的な甘みに、海胆の濃厚な甘みがかぶさる。
土佐酢は出汁が強めで、酸味は控え目。
強い甘みが抑制されており、気の利いた味付け。
噴火湾の毛蟹
提供温度が素晴らしい。
毛蟹の温度とシャリの温度がピタリと合っている。
よって、蟹の旨味と香りを感じられる上に、
シャリの酸味と甘み(米由来の)が混ざり、味覚のバランスが取れている。
尚、親方は「毛蟹と私の酢飯を混ぜた蟹鮨です」と料理の紹介をされたが、
「酢飯」ではなく「私の酢飯」と仰った点が琴線に触れた。
酢飯は鮨の魂なので。
鮟肝
余市産。鰹出汁で炊いており、きめ細かくねっちりした食感。
抜群に旨く、軽い血の香りもある点が面白い。
鰹出汁は強めで、甘みも利かせており、円みを帯びた炊き地である。
鮑
切り付けた瞬間に充満する、この香りもご馳走。
唐津産との事だが、香りに加えてゼラチン質が半端ない。
柔らか過ぎず、むっちりした食感も良い
食べている時もグイグイと香りが押し寄せ、この鮑にはビックリ。
前回伺った際、海の鰻に驚嘆を覚えたが、今回覚えた驚嘆に値する素材はこの鮑。
鮑の肝
炊き込んでいないので、ぷりぷりしておらずトロトロで塩辛的な肝。
ダイレクトに磯と鮑の香りを楽しめるが、臭みは無いのが良い。
鮎
郡上産。香り良く、焼きも鮨店としては中々。
季節を代表する鮎を出す心意気は素晴らしく、鮎好きとして大変嬉しかった。
ただ、振り塩はもう少し抑えても良いかと。
蓼ではなく木の芽と合わせるセンスは素晴らしい。
個人的には、ド定番の蓼酢は鮎の魚味を引き立てるとは思えないので。
この後、握りに移行します。
ガリ
カリッとした食感で、甘みと旨味が強い。
辛味は優しく、ふんわりと漂う。
アオリイカ
3日寝かせた呼子のアオリイカ。
厚めの切り付けで、細かい隠し包丁も入れない。
一口目からトロリとさせず、噛み締める程にトロトロ感が高まる。
めっさ甘い。
寝かせて引き立てた甘みを、包丁によって活かし切っている。
鮃
志賀島産。朝に〆たものだが、強いシャリに負けない旨味。
そして、僕好みのしっかりした食感、そして強い香り。
余韻も十分で、旬を外しているにも関わらず、玄界灘の凄さを証明する一貫。
金目鯛
銚子産。炙る事が主流だが、敢えての炙り無し。
ぷりぷりなのにとろけてゆき、香りが高まる。
旨味もどんどんどんどん高まり驚き。
塩で〆、皮は軽く湯霜にする仕事が金目鯛に新たなる魅力を与えている。
これも圧巻の仕事。
新子
「福岡で、しかも高い相場なのに出されるんですね!」とお伝えしたところ、
「弟子がいるので…」とはにかんで答えられる姿は、格好良い。
新子を美味しい魚として称賛する自称美食家の方が散見されるが、
新子は旨味ではなく香りを楽しむもの。
そして実際に楽しめた。
また、最大の面白みは、夏に鮨店を巡る事で小鰭の成長を追う事にある。
小鰭
キッチリ小鰭も出される点は尚更格好良い。
鮨好き冥利に尽きる流れ!
強めに締めて2日寝かせており、ひたすら旨味が凝縮されている。
媚びの無い〆加減で、シャリとの相性が良い。
鮪赤身
境港産。漬け。
巻き網船団が鮪を蹂躙している境港のものだが、
これは身焼けとは程遠く、鮪の旨味と酸味、
シャリの一体感が非常に高い。
シャリの味付けもあるが、それ以上に鮪の扱いが巧い。
鮪中トロ
こちらは大船渡産で、66キロの定置網。
トロの甘みとシャリの酸味が一致した満足度の高い一貫。
鯵
出水産。提供温度は低く、鮪の後なので敢えて冷たくしているそう。
成程…脂と風味が強い鮪の後に、爽やかさを感じさせる。
しかも、信じられないくらいの旨味で、冷えているのに舌を喜ばせる。
さらに、香りが残響のように残る。
徹底的に甘いが、鯵を食べた喜びを残す。
今までに頂いた出水の鯵の中でも、とりわけ印象深いモノであった。
そして、圧巻のストーリー性。
車海老
五島産。
身が厚く香り豊かで甘みが横溢する。
ひたすら旨い。
茹で上げで温度の馴染ませ方も良い。
鰯
対馬産。酢で軽く〆て、炙る仕事。
〆るだけでは味わえない、鰯特有の香りが引き立てられている。
即ち、干物的な香ばしさ。
更に軽い苦味と、それを凌駕する旨味が到達し、シャリの酸味が支える。
気付いたらとろけて消える。
水茄子の浅漬け
岸和田の水茄子。
蛤
九十九里産。
しっとりながらにシャクッとした食感も残す火入れと漬け込み。
そして、濃厚な煮ツメ。
東京でも少ないレヴェルの煮蛤の仕事。
キタムラサキウニ
はだての海胆。これも温度帯をコントロールされており、抜かり無し。
椀
ボタン海老の頭、九絵、金目鯛の頭を用いた椀。
味噌は控え目で潮汁の魅力を楽しませてくれる。
中でも九絵の香り強いと旨味が鮮烈。
穴子
とろとろフワフワな穴子。
そして、濃厚な煮ツメ。
確信したが、とろとろフワフワな仕上げの穴子が活きるのは、
あくまでもクラシカルな濃厚な煮ツメを用いるからではないか。
昨今とろとろフワフワな穴子に、サッパリな煮ツメを用いる事が一般化しているが、
旨味と風味よりも甘みが先行し、穴子の野趣を殺すとともに、味覚的なもたつきを覚える次第。
矢張り、煮ツメは濃厚でなければよろしくない。
べったら漬け
干瓢巻
硬く戻し、醤油の味わいは強めで、もちろん山葵を使用。
最後まで高い満足感を覚えた。
今回はやや多めにお酒を飲んで、トータル24,000円ほど。
同じ価格帯の鮨店、日本料理店、ひいてはフランス料理店などと比較しても、
決して高くは無い、非常に満足度の高いコースだと思います。
次回訪問するのが楽しみになる名店。
本記事は下記のブログをベースに投稿しております。
すしログ:https://sushi-blog.com/